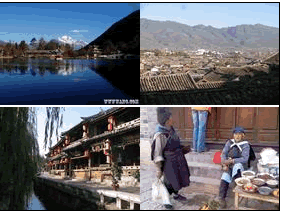4.1 はじめに
中国の医薬品市場はこの5年間で2.5倍になり、2010年には約3.5兆円の規模にまで成長しています。これは日本に次いで世界第3位でこの成長が持続すると、2015年にはアメリカに次いで世界第2位になるという予測もあります。中国は「世界の工場」から「世界の市場」へとシフトし、今後は上海張江ファーマバレーを代表とする国家生物産業基地が「世界の研究開発センター」になると筆者は見ています。
一方、中国の医薬品に関わる法規制は複雑でかつ頻繁に改正され、外国企業にとっては頭痛のタネとなっています。例えば、この2年間に次のような医薬品行政に関する大きな制度改革がなされました。
1.3ヶ年医薬衛生体制改革
2.薬価制度改革
3.新GMP施行
4.流通制度改革
このような改革の目的はすべてに共通しており、「より安全で品質の良い医薬品や医療サービスをすべての国民に提供できるようにすること」にあります。それではこのような制度改革により、医薬品業界はどのように変化するのでしょうか。これらひとつひとつについて検証してみたいと思います。
4.2 3ヶ年医薬衛生体制改革
中国の内閣にあたる国務院は2009年4月、『医薬衛生体制改革短期重点実施方案(2009-2011年)』を公布しました。同方案では、3年間で総額8500億元を投入し、抜本的な医療改革を実施していくことを明らかにしました。その内容は次の5項目です。
1.基本医療保障制度の構築推進
2.国家基本薬物制度の基本構築
3.末端医療サービス体制の整備
4.基本公共衛生サービスの均等化
5.公立医院改革の推進
本医療改革に総額8500億元(約11兆5000億円)という膨大な予算が組まれたことにより、医薬品市場から見た場合、直接的または間接的に好影響を与えることは容易に想像できます。「基本医療保障制度の構築推進」によって、すべての国民が適切な医療を受けられるようになり、その結果、受診、治療機会が増え、医薬品の処方の増加に繋がるからです。農村の労働者を対象とした新型農村合作医療制度および都市部労働者を対象とした都市従業員基本医療保険制度が充実し、さらに普及が進むと受診患者が増えるのは間違いありません。
次に「国家基本薬物制度の基本構築」ですが、これは基本となる薬物の供給を保障し、出来るだけ多くの患者が治療を受けられるようにする制度です。2009年8月には国家基本薬物目録、同11月には国家基本医療保険薬品目録が公表されました。前者は各治療領域での基本薬物を制定しており、この目録に入ると保険償還を規定する基本医療保険薬品目録で償還の対象となるため、市場優位性を保つことができます。
例え薬価が低く抑えられてもそれ以上の市場の伸びが期待できます。また政府補助政策の恩恵を受けることになり、企業は大きな利益を得ることになります。したがって、新薬メーカーは新薬承認取得後、国家基本医療保険目録への収載に向けた作業に全力を挙げて対応しなければなりません。また、公立病院改革により医薬品のマージンに大きく依存していた病院経営が医療技術サービスなど本来あるべき医療報酬などにより運営されるべきと定義付けしています。そうなれば適正な医薬品の流通や商取引きが行われ、健全な市場が形成されると考えます。
4.3 医薬品流通と市場改革、外資参入の推進
2011年5月、中国の商務省が医薬品の流通改革に乗り出しました。大型卸や販売企業の育成、外資系企業の参入を推進し、流通網の近代化を図り、地方都市や農村部で良質の医薬品を低価格で浸透させるのが狙いです。中国では医薬品の卸や販売業者が乱立し、非効率な流通網が医療費を膨らませる要因にもなっていました。そこでこの流通改革により、医療費を抑制し、少子高齢化社会の到来に備える狙いもあります。
具体的には「全国薬品流通業発展規則綱要」には年商1000億元(約1兆3000億円)を超える大型医薬品流通企業を2015年までに1~3社育成。業界再編を通じて上位100社の医薬品卸企業で全国シェア85%以上を、医薬品小売りチェーン上位100社で60%以上のシェアを占めるようにするとしています。
また、外資系卸の参入を奨励し、国内企業への出資や流通網の整備が遅れている内陸部への進出を促すのが狙いです。さらには中国企業に対して株式市場や海外市場への進出を後押しし、世界的な医薬品調達・販売網の構築を目指すとしています。すでに中国医薬品卸大手の国葯集団や上海医薬集団は香港市場に上場しました。今後は製薬企業にとっていかに有力卸と強力なパートナーシップを構築するかが、売上拡大のカギを握ると言えるでしょう。
4.4 最高小売価格の値下げ
中国の薬価行政を司る中国国家発展改革委員会は2010年11月、一部の単独定価医薬品の最高小売価格の値下げを開始する一方、いくつかの医薬品の単独定価資格を取り消し、新薬の値下げ方案を発布する」と通知しました。今回の値下げ幅はおよそ平均約15%になると予測されています。
医薬品価格の調整は迅速に実行され、多くの国産医薬品が値下がりしました。307品目の基本薬物の中での国産医薬品の薬価下落率は約40%に達しました。委員会はさらに、これまで単独定価にあった外資輸入薬に対しても平均19%に達する値下げを行いました。
医薬品薬価の値下げにより国内外の医薬品メーカー間の利益率の差が縮まり、将来的に海外メーカーは国内メーカーの市場占有率が同じ程度になるとの予測もあります。現在、中国の三級甲等医院で使用される医薬品のうち、7割以上が海外メーカー品で、3割弱が国産メーカー品と言われています。一方、二級以下のクラスの医院では、逆に国産メーカー品が圧倒的に多く使われているのが現状である。
したがって、海外メーカーは地方都市の2級医院などこれまで手薄であった市場への参入、販売強化が成長のカギを握ると言えます。
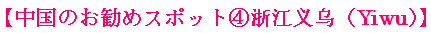 世界最大の商品卸市場をご存知でしょうか。それは
世界最大の商品卸市場をご存知でしょうか。それは です。医薬品関係の方には馴染みがないかもしれませんが、雑貨、衣料品などの商品の仕入れに関わる方はご存知の方も多いと思います。上海から車で4時半、今話題(?)の新幹線に乗ると2時間ちょっとです。世界中からバイヤーが買い付けにきます。その数は1日平均20万人とも言われています。もちろん、個人でも大丈夫です。
です。医薬品関係の方には馴染みがないかもしれませんが、雑貨、衣料品などの商品の仕入れに関わる方はご存知の方も多いと思います。上海から車で4時半、今話題(?)の新幹線に乗ると2時間ちょっとです。世界中からバイヤーが買い付けにきます。その数は1日平均20万人とも言われています。もちろん、個人でも大丈夫です。
店の数は2万店舗以上で雑貨、工具、電子機器、玩具、装飾品、化粧品、おもちゃ、意類、靴、小物雑貨はすべて調達できます。価格は通常、市価の20%~50%くらいでしょうか。もちろん、交渉次第ですから、簡単な中国語を駆使して値切るのは当然です。「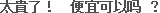 (高い!安くしてくれる?)」は必須フレーズですね。
(高い!安くしてくれる?)」は必須フレーズですね。
値段の例で言うと通常の紳士靴、婦人靴は50~100元(650~1300円)、ラジコンヘリ60~150元(800~1800円)といった感じです。日本で買えばそれぞれ3000~6000円、2000~8000円くらいでしょうか。
ここはほとんどの日本の100円ショップが買い付けにきたり、あるいは地元の製造会社に大量生産を委託したりすることでも有名です。興味のある方はぜひ、訪ねてみて下さい。

第3回 [ 製薬企業の世界戦略 ~大塚製薬と武田薬品の考察~ ]
3.1 はじめに
激動の時代を迎えた世界の製薬企業はどのように生き残りを図ればよいのでしょうか。そして日本の製薬企業の取るべき道は?大型製品の特許切れ、ドラッグラグによる承認の遅れ、新薬の枯渇など現在、製薬企業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。いや、これからの10年はなお一段と厳しくなることが予想され、製薬業界は大きな転換期を迎えていると言っても過言ではありません。
研究開発は製薬企業にとって生命線であることは周知のことですが、研究開発コストは年々、膨大なものになりつつあります。例えば、外資系企業ではファイザーの86億ドルを筆頭にサノフィ・アベンティス67億ドル、グラクソ・スミスクライン65億ドル、日系ではトップの武田が4500億円、アステラス1590億円、第一三共1850億円といずれも巨額の研究開発費を投じているのです。これらの研究開発費は各社の売上の15~20%を占めており、他の産業のそれを圧倒しています。私が医薬業界に入った1978年頃は1つの新薬を開発するのに10年、100億円と言われていましたが、今は15年、500億円とも言われています。それにも関わらず、上市される新薬は年々、減少しているのが現状なのです。
そこで各社はM&Aや海外市場開拓を加速させているわけです。すなわち、グローバル戦略の強化です。
武田薬品は製薬業の発祥の地とも言える大阪道修町に産声を上げ、着実に成長してきた、言わば「老舗中の老舗」です。日本の製薬業界にあってはトップ企業として長らく君臨しています。1970年~80年代は新薬がなかなか出ず、冬の時代でしたが、米国での製品戦略および臨床開発の成功により、一気にその実力を花開かせたと言えます。前立腺がん治療薬のリュープリンを皮切りにタケプロン、ブロプレス、アクトスの製品を欧米市場に上市し、いずれも1000億円を超える大型製品となり、会社全体の売上の6割近くを占めるようになりました。
一方、大塚製薬は徳島県鳴門市が発祥の地で当初は製塩の製造過程で出てくる無機化合物を製造販売していました。無機化合物は大手製薬メーカーに医薬品原料として販売していましたが、その後、これを輸液にして製造販売したのが医薬品製造の始まりです。その後、オロナイン軟膏、オロナミンC、ポカリスエットなどのヒット商品から得られた利益を新薬の研究開発に投入し、自社開発医薬品の成功へと繋がったのでした。大塚製薬の海外展開はまず、日本で独自に開発したプラスティックボトル入りの輸液をタイ、インドネシア、中国で製造販売を開始したのが最初です。その後、自社での新薬研究開発が実を結び、国内だけでなく欧米でも早い段階から開発に取り組みました。1980年にドイツフランクフルト、1985年には米国メリーランド州に臨床研究の拠点を置き、開発を進めたのでした。そして米国で自社開発3番目の製品となる統合失調症治療薬のアリピプラゾール(米国販売名「Abilify」)は世界の売上が4000億円近い超大型製品に成長し、会社のグローバル化にも大きく貢献しました。
本コラムでは日本を代表し、海外事業に積極的に取り組む2つの製薬企業の対照的なグローバル戦略を検証し、今後の日本製薬企業の歩むべき道について考察してみたいと思います。
3.2 武田がアメリカで成功した背景とは
武田のアメリカ進出は1985年、米国での自社製品販売を目的としてアボット社と合弁会社TAP社(Takeda Abbott Pharmaceutical Inc.)を設立したのが最初です。当初、本社サイドは日本で主力製品であった抗生物質を販売するという計画を持っていて、すでに現地工場は完成し、抗生物質の製造承認も取り、稼働目前でした。ところが、当時、本社から現地に赴任していた武田國男氏がこれに「待った」をかけたのでした。これを知った他の多くの現地駐在員は困惑していたそうですが、同氏と1名の部下と抗生物質の徹底的な市場調査、他社動向の分析を行い、やはり抗生物質では投資回収は難しいと判断しました。そこで同氏は前立腺がん治療薬「リュープリン」に切り替えるべきだと主張したそうです。当然、本社役員は反対でしたが、それを説き伏せて「リュープリン」の販売に至ったという経緯があります。
この話は伝説的な意思決定として業界では有名な話ですが、この海外現地の事情をつぶさに察知し、信念を持って会社の方針を変えさせたことが、その後の同社のアメリカ事業大成功に繋がったものと思うのです。
一方、大塚製薬は1970年代前半からタイやインドネシアで輸液の現地製造販売を始め、これが海外進出の始まりです。アメリカは当初、パロアルトやニューヨークにリエイゾンオフィスを設けていましたが、本格的に活動を開始したのは1985年、メリーランド臨床研究所を作ってからです。ちょうどその時期は自社の医薬品研究が実を結び、新薬が次々と臨床開発の段階に入っていました。同社は日米欧の3極同時開発の方針を打ち出し、グローバル開発を進めたのでした。私は1985年、フランクフルト研究所に駐在していましたが、そこでの臨床研究は主としてアメリカでの臨床開発をサポートするためのものでした。その後、アメリカの開発部隊は合成抗菌剤、抗血小板薬の開発を成功させ、上市しましたが、残念ながらビジネスとしては成功というところまで行きませんでした。ところが、米国で3番目の自社開発品であるアリピプラゾール(米国販売名Abilify)はBMSという強力なパートナーを得てメガドラッグとなったのです。粘り強く、アメリカで開発を続けてきた努力が実ったわけで「3度目の正直」と言えるかもしれません。
3.3 他を圧倒する大塚の中国・アジア事業展開
大塚はアジアからグローバル展開を進めたとお話しましたが。1973年、タイにタイ大塚製薬を設立し、輸液の現地製造・販売を開始しました。その後、インドネシア、台湾、パキスタン、エジプト、ベトナムに次々と進出しています。
中国においては1981年、外国企業として合弁第一号となった中国大塚製薬有限公司を天津に設立したのでした。改革開放が打ち出された直後の1978年、外資系企業で本格的に中国に進出する企業がない状況で中国の経済発展を予測し、英断を下した経営トップの意思決定は特筆に値すると言えます。
2000年代に入ると同社はさらに中国事業を加速させ、2003年には持ち株会社に当たる投資公司を上海に設立し、さらなる事業展開を進めました。私が上海に駐在したのもこの時期で医薬品の他、飲料(ポカリスエット)や食品(ソイジョイ)などの消費者商品市場にも参入しています。
同社は中国にグループとして既に20社以上の現地法人を設立し事業活動しています。日系企業の中では群を抜いているのではないでしょうか。
一方、武田は大塚の進出から13年後の1994年、自社医薬品の製造工場設立・販売を目的として力生製薬と75:25の合弁企業、天津武田薬品有限公司を設立しました。武田の主力製品である前立腺がん治療薬「リュプーリン」、去痰剤「ダーゼン」、降圧剤「ブロプレス」、糖尿病治療剤「アクトス」などを販売しています。
しかしながら、武田の場合は欧米での4つの大型製品の成功により、中国を含めたアジア事業は社内でのプライオリティが低かったものと考えられます。
このことは本体売上の約60%が欧米市場から来ることを考えれば、当然であるとも言えます。ただ、主力製品の特許が次々と切れて欧米での売り上げが落ちることは避けられず、これをどのようにカバーするかが、今後の課題と言われています。
そこで、同社は米国のミレニアム、スイスのナイコメッドを巨額の資金で買収し、製品パイプラインの拡充とグローバル市場での販売力の強化を図っています。また、中国において今年に入って、上海に投資公司、江蘇省泰州に新しい販売会社を設立し、中国事業強化を打ち出しています。新会社は輸入薬の販売および卸の許可証を取得し、製品パイプラインを強化し、またMRを900名体制に増強し、売上を伸ばす計画を立てています。計画を実現するためには開発スピードと承認取得、それに販売力がカギになると見られます。
3.4 経営トップのグローバル志向
武田と大塚のグローバル戦略において注目すべきは経営トップのグローバルマインドが共通している点です。
武田薬品の長谷川閑史社長、大塚ホールディングスの樋口達夫社長、大塚製薬の岩本太郎社長はいずれも米国駐在を長く経験し、欧米流の事業戦略を熟知され、また独自のグローバルマインドを持っておられます。この3名の方々とは一緒に仕事をさせて頂いたり、あるいはお会いさせて頂いたことがありますが、グローバル志向が極めて顕著であると感じました。筆者はこの3名の経営者の方々の足元にも及びませんが、米国、欧州、中国に駐在し、海外の実情を肌で感じ、ビジネスを体験しました。やはり、グローバル事業のマネジメントには海外に根を下ろし、身体で感じた経験は不可欠と考えています。また両社のグローバル化を推進された武田薬品の武田國男前会長、大塚ホールディングの大塚明彦会長はそれぞれの会社で海外戦略を迅速に決定され、今日のような超グローバル企業に育てられました。このご両名が自ら現場で陣頭指揮され、現地社員を指導された経営手法はグローバル化に不可欠と言えます。
このような両社のグローバル戦略経営は他の製薬企業や他の産業にも相通じるものがあるのではないでしょうか。
【 中国のお勧めスポット③ 湖南省韶山(Shaoshan)】
中華人民共和国建国の父である毛沢東の故郷が湖南省であることは有名ですが、この地を訪れた日本人は少ないのではないでしょうか。私は仕事で中南大学湘雅医院を訪問した際、運よく(?)、週末にかかったため、訪問しました。毛沢東が生まれ育った家は正確には湖南省湘潭県韶山村という池や田んぼに囲まれた農村にあります。省都の長沙から車で2時間くらいでしょうか。ここには生家の他、毛沢東博物館や巨大な像があり、全国から大勢の人がやってきます。生家の見学には行列が出来、30分~1時間、待たなければなりません。この小さな町には「毛」という名前の湖南料理店がいたるところにあります。博物館には幼少の頃から成人し共産党での活動、中国人民共和国建国など彼の生涯が展示品や写真と共に展示、解説してあり、中国の歴史が読み取れます。中国通の方には外せないスポットでしょう。
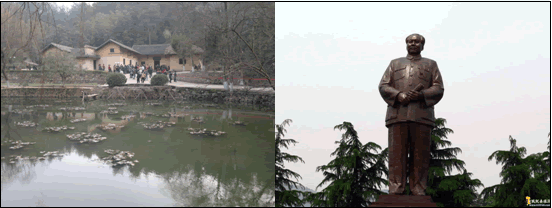
第2回 [ グローバル・アライアンスと成功事例(2011/9/20)
「アリピプラゾール(Abilify)~425日間の記億~」 ]
1.1 プリンストンの夏
1999年8月1日。ニュージャージー州プリンストン。湿度はそれほどでもないが、日差しがきつく外に出ると汗が吹く出すくらい暑かった。私はここのホテルで明日の契約交渉の打ち合わせをしていました。メンバーは私を含めて4人。私の上司であるライセンス担当常務、法務部の契約担当部長、それにシアトルにある法律事務所の顧問弁護士、そして筆者(当時、国際ライセンス部シニア・マネージャー)の4人です。私たちはブリストルマイヤーズ・スクイブ社(以下、BMS社)と統合失調症治療薬「アリピプラゾール」(米国販売名:Abilify)の最終交渉のため、BMS社の研究開発センターのあるこの地に乗り込んできたわけです。
前日は朝から交渉を始めたものの、ある契約条項で平行線となり、30分という短い時間で交渉打ち切りとなってしまいました。契約交渉は粘り強くやることが鉄則ですが、さすがに交渉開始後30分で平行線、かつ歩み寄りの手がかりがなくなったことに一同、気落ちしてしまいました。我々は直ぐにホテルに戻り、カフェテリアで打開策を練って、明日の交渉で何とか前に進めたいと考えていました。この契約は通常のライセンス契約と異なり、共同開発契約、共同商業化契約、一部ライセンス契約という複雑な構造になっていた点や社内の諸事情も重なって、最初の契約交渉が始まってすでに1年を越えていました。そのため、我々は今回のプリンストン出張ですべての条件において何とかして契約合意に持っていきたいと考えていたのです。
その後もBMS社と難解な交渉が続き、胃に穴が思いでしたが、7月29日~8月4日までの1週間をかけて最後の息詰まる交渉を乗り越え、BMS社と合意に達することが出来ました。最終日は交渉のあと、ホテルに戻り、全員、疲れが頂点に達していましたが、安堵感と同時にこの1年半に亘る契約交渉が合意に達し、BMS社という強いパートナーを得たことで、アリピプラゾールの成功を確信いたしました。その年の9月20日、ニューヨークにあるBMS社の本社ビルで調印式が取り行われ、この製品の成功への道がスタートを切ったのです。最初の契約交渉から調印まで実に435日間の道のりでした。
1.2 波乱の425日間
アリピプラゾールは現在、世界の約70ケ国で販売され、売上規模は約3800億円近くに上ります。大塚製薬の2011年3月期の売上が約5000億円ですからこの製品が会社に取って如何に重要かが伺えると思います。この製品は日米欧で自社開発していましたが、1998年にBMSとのアライアンス話が浮上するまで、社内にはこのような大きな製品になることを予測していた人は誰もいませんでした。というのも当時の日本の統合失調症治療薬の市場が100億円程度だったからです。米国ではヤンセンのリスパダールやイーライ・リリーのオランザピンの売上は数千億円規模でしたが、日本の会社が米国で、しかも中枢系の医薬品の販売を単独でやる限り、大きな売り上げを挙げることは難しいとされていたからです。実際、当時のアメリカ子会社の販売計画はせいぜい数百億程度でした。
BMS社との共同開発・共同商業化契約は険しい道のりで長い時間を要しました。会社が自社開発自社販売の方針から他社とのアライアンス方針に転換したのは1998年2月です。私はそれよりずっと前からこの製品をグローバル製品に育てるには巨額の資金力と強力な開発・販売力が求められ、しかるべきグローバル企業との提携は不可欠と考えていました。そこで本製品が欧米においてフェーズⅡが終了した1996年初頭から他社面談の際、相手先企業の財務状況、開発パイプライン、重点治療領域、過去のアライアンス実績、精神科領域の強さ、またこの製品に対する興味レベルなど詳細に情報収集しました。そしてアライアンスパートナー候補会社のリストを作成し、これをアップデイトし、いざというときのために準備していたのです。
そして1998年2月、その決断は下ったのでした。国際ライセンス部では直ちに作成していた候補会社、10社を訪問し、興味の打診、我々の希望する基本的な契約スキームが受け入れ可能かどうか、などを確認しながら、交渉を開始しました。
最終的にグローバル企業3社と秘密保持契約を結び、度重なる面談や交渉の結果、最も熱心でかつ熱意を示してくれたBMS社と契約することになりました。最終的にこの会社に決定した理由はこちらの多大な要求を受け入れてくれたことやこの製品に対する強い熱意でした。たとえば、BMS社との最初の面談時(秘密保持契約締結前)にCEOを含む約20名が顔を揃えました。初期のライセンス交渉は担当者レベルで面談するのが通常ですので、これには当方4名は驚くまかりでした。それだけ、興味を持っていて熱意も感じたものです。BMS社は本格的な契約交渉の過程でこの製品の臨床データがあまりにも少な過ぎる点を指摘しました。実際、大塚アメリカで行っていた試験は米国食品医薬品局(USFDA)に申請する最低限のものでした。
そこで、BMS社は上市までに追加で40本近くの臨床試験を行い、そのために数百億円を投入してマーケティングのためのエビデンス構築を提案してくれました。このようなマーケティング手法は欧米のグローバル企業ならではのやり方で、承認を取っても製品が売れなければ意味がないという考え方です。多くの追加試験は上市までにエビデンスが得られ、今のような大型製品に成長したものと思っています。
この契約交渉は本当に難航を極めました。すでに述べたように通常のライセンス契約と異なり、共同開発、共同商業化、一部はライセンス契約という複雑なスキームで、また契約自体も大型であった(BMS社として会社始まって以来の最大のディールでした)こともあり、1年半を要したわけです。一端は合意に達し、調印式まで決まっていたにも関わらず、それが白紙に戻るという事態もあって、ライセンシング担当者としては胃に穴が開く思いをしたものです。しかし、そのような苦労が今日のパートナーとの良好な関係を築き、世界に認知される大型製品にまで成長したことはそのアライアンス担当者として誇りに思っています。
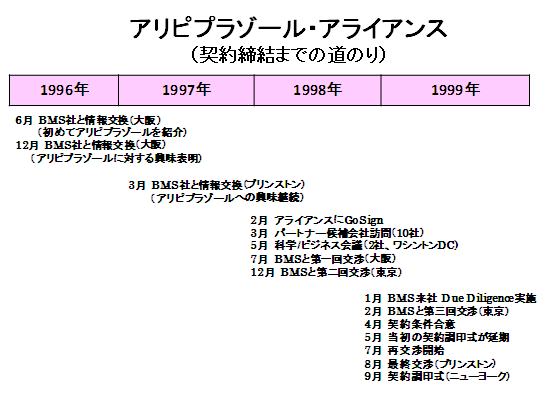
1.3 グローバル・アライアンス
医薬品の研究開発は製薬企業にとって生命線であることは言うまでもありません。特にこの5年~10年、大手企業の大型製品の特許切れが相次ぎ、これらの製品を抱える企業はあらゆる手段を講じて、売上の落ち込みをカバーしようとしています。ファイザーはこれまでワーナーランバートやファルマシア・アップジョンを買収しましたが、さらに昨年、ワイスを買収するなど、次々と大型M&Aを行い、規模を求めて生き残りを図っています。日系企業でも武田薬品はミレニアム社を8800億円、ナイコメッドを1兆1000億円という巨額で大型買収を行いました。
各国厚生当局による新薬審査の厳密化、安全性評価の基準の高まりなどにより、世界的に新薬が出にくくなり、また研究開発コストも膨大なものになっていることも大型買収の背景にあると言えます。たとえば、製薬企業の研究開発費はファイザーの86億ドルを筆頭にサノフィ・アベンティス67億ドル、グラクソ・スミスクライン65億ドル、日系ではトップの武田が4500億円、アステラス1590億円、第一三共1850億円と各社売上の15~20%を占めています。
それでも、新薬開発のハードルが高くなるにつれて研究開発投資は膨らむ一方で、成果物である新薬は逆に出にくくなる傾向になっており、年々、減少するという現象が起こっています。したがって、製薬企業は研究開発の投資効率を上げるため、ICHの概念も踏まえた形で国際共同試験を多く取り入れ、迅速にかつ効率良く臨床試験を実施し、各国申請に耐えうるデータの集積、またそれをベースに承認申請を行うというスキームが一般化してきています。
以上のように大型製品の特許切れ、研究開発費の膨張、新薬パイプラインの欠乏などの理由により、他社からのライセンシングやM&Aが以前にも増して活発に行われるようになりました。医薬品は創製した企業がどのような会社であれ、またどの国であれ、世界市場を見据えたビジネス展開が不可欠です。そこで自ずとボーダーレスのアライアンスが盛んに行われるわけです。
私は新薬開発を14年間経験したのち、縁があってライセンスの仕事に就きました。私に取ってライセンスの仕事は初めての経験であり、開発職とまったく異なり、新鮮でした。開発の仕事はある意味、狭く深く学ばなければなりません。医薬品の毒性学、薬理学、薬効評価、臨床試験の企画、統計解析、製造承認申請に関する薬事などは開発部員にとって不可欠の知識です。私のように工学系の人間にとってはほとんどが「一から勉強」という状況でした。
一方、ライセンスの仕事はどうかというと、自社の中長期事業計画、研究開発方針、製品パイプライン、マーケティング戦略、生産計画、海外事業戦略、市場、価格、他社の開発動向などをまず、熟知しなければなりません。またライセンス契約の交渉には貿易、会計、税務、契約法などの知識も求められます。他社からの製品導入、他社への導出というライセンス業務には他社との情報交換も不可欠です。そのため、まず会社案内や会社資料を隅々まで読んで理解し、必要に応じて関連部門から情報を得て、会社のプレゼン資料を作成します。
ライセンス案件はほとんどの場合、他社との情報交換から始まることが多く、したがって、他社のライセンス担当者との交流は最重要業務のひとつです。このいわゆる情報交換は国内、海外の製薬企業は言うに及ばず、バイオベンチャー、大学や政府の研究所、ベンチャーキャピタルまで数多くの団体、機関と行います。目的は明確で他社から導入の可能性がある製品情報を収集すること、逆に自社製品を他社へ導出する場合の興味の打診、導出先として相応しい会社かどうかを判断するための企業情報の収集です。
ライセンス部門に異動して間もない頃は、自社の会社紹介(プレゼン)さえシドロモドロの状態で、とりわけ、海外の製薬企業との情報交換は頻繁で英語で行うこともあり、当初は英語にかなり苦労しました。英語力そのものの問題と技術的、専門的用語を覚えるのにはかなり悪戦苦闘したものです。昔の英語教科書、ビジネス英会話など通勤時や出張の際、随分、勉強しました。また、アメリカへ出張の際はBarnes & Nobleなどの本屋に立ち寄り、ビジネス書、契約法、交渉学などの本を買い漁って学習しました。大学受験以来、これほど勉強に打ち込んだのは久しぶりでした。ただ、外国企業との面談や情報交換も回を重ねる毎に慣れとコツを覚え、自信を持てるようになりました。
1年も経つと1人で海外出張し、世界のグローバル企業と面談することが苦にならず、むしろ自信がついてきて、面談企業から色々な情報を得ることが逆に楽しくなってくるのです。私がライセンスの仕事を担当した1995年~2002年は丁度、大塚製薬の欧米での臨床開発が活発に行われていた時期で、有力製品の開発も最終段階に差し掛かっていました。そこで海外市場でのさらなる開発や販売パートナーが不可欠となり、他社との面談に拍車をかけたと言えます。アリピプラゾールの他、抗菌剤のグレパフロキサシンや抗血小板薬のシロシタゾールのアライアンスにも関わり、実戦経験できたことは運命的なものだったのかもしれません。
このように大塚製薬のグローバル化戦略の真っ只中で関連する部門で重要な仕事をすることが出来たことは幸運だったと思いますし、また私自身の財産となりました。
【中国のお勧めスポット② 麗江(Li Jiang)】
麗江は雲南省の北部に位置し、納西(ナシ)族の暮らす小さな街です。しかし、玉龍雪山から湧き出てくる清水を湛える玉泉公園、それに4000を超える民家が集中する麗江古城は中国の歴史を感じさせます。まわりには城壁がなく、伝説によれば、古代に木氏という領主がこの一帯を支配し”木”を城壁で囲むと“困”の字になるから嫌ったのだと言われています。
以前は雲南とチベットを結ぶ交易路の要衝拠点で800年前から発展したそうです。そのため建物も商店としての機能を持ったものが多く、ほとんどが二階建て。有名な四方街を中心として、周囲へ向かって、麗江で生産した五花石で敷きつめられた石畳の路地が放射状の分布をしています。その間を城頭から三本の清らかな疎水が走り、明清時代の石のアーチ橋と石板の橋が約300、架かっています。民家はすべて木造のかわらぶきの家、古色豊かな古代建築の傑作です。1997年、世界文化遺産に登録されて、土地の少数民族である納西族が作り出した優れた文化財と言えます。