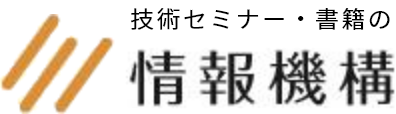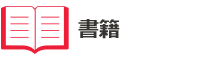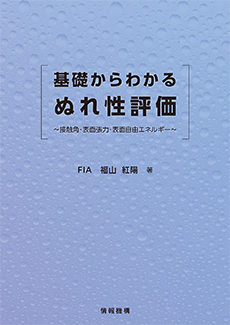発刊・体裁・価格
発刊 2025年9月10日
定価 〇書籍版のみ:44,000円(税込(消費税10%)) 〇PDF版(CDーROM)のみ:44,000円(税込(消費税10%))
〇書籍版+PDF版セット:55,000円(税込(消費税10%))
体裁 A4判 292ページ 書籍版モノクロ PDF版カラー
ISBN 〇書籍版 978-4-86502-289-6 〇PDF版(CD-ROM) 978-4-86502-290-2
★PDF版(CDーROM)の仕様について【必ずご確認下さい】
・書籍全文掲載・書籍版は図表はモノクロですが、PDF版ではフルカラー掲載となります。
・本文中のURLに関しましては、執筆参照時の物であり、現在リンク切れになっている場合もございます。
予めご承知おきください。
・本文コピー不可。印刷不可。商品ごとに、ファイルデータへ個別のパスワードを設定
・購入者様毎にシリアルナンバーを設定。各ページに記載あり(なお購入者以外の方が不法に利用する事は禁じます)
・パスワードはCD-ROMに添付されています
※書籍版のみ/PDF版(CDーROM)のみ/書籍版+PDF版(CDーROM)セットのいずれかをお申込みされるか、選択下さい
※本品については著作物であり、複写・配布、無断転載は固くお断り致します
→詳細、申込方法はこちらを参照
→書籍を購入された方へ(アンケートのお願い)
著者
FIA 福山 紅陽 氏 【著者紹介】
1993年3月 : 東京工業大学大学院 理工学研究科 無機材料工学専攻 修士課程 修了。
1993年4月 : 三菱マテリアル株式会社 入社。
分析評価部門で,XPS(X線光電子分光装置),SIMS(2次イオン質量分析装置)のオペレーション,解析,分析技術の高精度化に従事。
1997年4月 : 協和界面科学株式会社 入社。
技術部門で,接触角計,表面張力計の研究・開発・測定業務に従事。
2010年10月 : FIA 創業。
ぬれ性評価を中心に,技術コンサルティングに従事。
本書のポイント
ぬれ性評価以前の基礎知識からわかりやすく解説し疑問点を解消!
これ一冊でぬれ性の評価がよくわかる!
充実した内容が好評の通信教育テキストを書籍版として大幅に加筆、再構成
★はじめにより 抜粋
本書は,ぬれ性の適切な評価に向けて,必要な情報を提供することを目標としています。ここでいう評価とは,具体的には,接触角測定,表面張力測定,表面自由エネルギー解析などの測定方法を検討し,実際に測定し,その結果を解析,解釈することまでを含みます。
~中略~
これまで,企業からぬれ性評価の相談を受けたり,セミナーや通信講座の依頼を受けたり,古巣の会社に出入りしたりして,様々な事例・相談・質問に向き合う機会がありました。
セミナーは時間的な制約が大きいので,内容をかなり絞らざるを得ません。それに比べると,通信講座のテキストでは,盛り込む内容をもう少し広げることができます。とはいえ,当初,テキストに盛り込んでいた内容は,ぬれ性評価そのものに関するものだけでした。
しかし,これまでのコンサルティングの経験では,相談者側の,ぬれ性評価以前の基礎知識や周辺知識が足りていないために,ぬれ性評価の方法,解析,解釈が適切ではなかったという事例も少なからずありました。ある依頼元からのデータを筆者が解析し直したことによって,彼らの結論がひっくり返ってしまい,その依頼元の開発目標が変わってしまったということもありました。このような事例を通じて,より基本的な内容や周辺知識も含めて啓蒙することの必要性を痛感してきました。筆者自身も,基本中の基本にまで立ち返って考え直すことの重要性を,日々実感しています。
このような状況のもとで,通信講座のテキストも,開講のたびに少しずつ書き足してきました。そして今回,あらためて書籍として出すという機会を得ましたので,内容構成を大々的に見直した次第です。
~中略~
本書は全16章からなります。
§1~§4は,いわば準備編です。最も基本的な物理を復習した後,全体像を把握するために,ぬれが関わる各種の基本概念を概観して,身近な例や産業上の例を紹介します。次に,測定に必要な基礎知識を説明します。ここで扱った項目だけでは決して十分とはいえませんが,これまでの経験から,筆者が必要性を特に感じたものを中心に取り上げました。さらに,ぬれ性評価に必要となる,表面・界面に関する基本的な知識を説明しています。
§5~§11は,理論編です。分子間力,表面張力,表面自由エネルギー,接触角などについて,概念や機構などを物理的側面から詳しく説明しています。
§12~§15は測定編です。接触角,表面張力,表面自由エネルギーの実際的な測定・解析方法や注意点について説明しています。
§16は,付録です。関係式の導出などを中心に,詳しく説明しています。
目次
1. 準備
1.1 量の表現
1.1.1 国際単位系(SI)
1.1.2 SI接頭語
1.2 力学
1.2.1 力
1.2.2 力の単位 ニュートン
1.2.3 万有引力と重力
1.2.4 仕事
1.2.5 エネルギー
1.2.6 エネルギーの単位 ジュール
1.2.7 ポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)
1.2.8 運動エネルギー
1.2.9 力学的エネルギー保存則
1.3 熱力学
1.3.1 熱力学の法則と自由エネルギー
1.3.2 ポテンシャルエネルギーと安定性
1.3.3 自由エネルギーと安定性
2. ぬれに関する各種基本概念
2.1 ぬれ性
2.2 表面と界面
2.3 親水性,疎水性,撥水性
2.4 ぬれ性と接触角
2.5 表面張力と界面張力
2.6 表面自由エネルギーと界面自由エネルギー
2.7 表面張力の由来
2.8 分子間力
2.9 ぬれ性と分子間力
2.10 表面自由エネルギーの成分分けと表面自由エネルギー解析
2.11 曲がった界面とラプラス圧
2.12 ぬれ現象が関わる事例
2.12.1 日常生活
2.12.2 産業
3. 測定に必要な基礎知識
3.1 測定値の信頼性に関する技術用語
3.2 測定の意義
3.3 知りたいこととわかることの違い
3.4 量の表現と単位
3.4.1 量と値
3.4.2 単位
3.4.3 国際単位系(SI)
3.4.4 SI単位と併用できる非SI単位
3.4.5 次元
3.4.6 無次元量(次元1の量)
3.4.7 SI接頭語
3.4.8 温度の単位
3.4.9 物質量の単位
3.4.10 角度の単位
3.5 データの要約
3.5.1 分布
3.5.2 基本統計量
3.6 母集団と標本
3.6.1 母集団
3.6.2 標本
3.6.3 有限母集団と無限母集団
3.6.4 測定値のばらつきと無限母集団
3.6.5 母平均と標本平均
3.6.6 母分散と標本分散
3.6.7 母標準偏差と標本標準偏差
3.6.8 母数
3.6.9 生データのばらつきと標本平均という量のばらつきの違い
3.6.10 母平均の区間推定
3.6.11 母分散・母標準偏差の区間推定
3.6.12 最小二乗法
3.7 ばらつきとかたより
3.7.1 ばらつきとかたより
3.7.2 ばらつきの原因と対処
3.7.3 かたよりの原因と対処
3.8 実験の3原則
3.8.1 実験の反復
3.8.2 実験の無作為化
3.8.3 実験の局所管理
3.9 数値の取り扱い
3.9.1 有効数字
3.9.2 有効桁数
3.9.3 有効数字の不確かさの解釈
3.9.4 標本標準偏差の値の有効桁数
3.9.5 有効数字どうしの計算
4. 表面と界面
4.1 物質の3態
4.1.1 分子の熱運動
4.1.2 分子間力
4.1.3 物質の3態
4.1.4 物質の状態変化
4.1.5 沸点と分子間力
4.1.6 超臨界状態
4.1.7 真空
4.2 表面と界面
4.3 バルク
4.3.1 バルクの3つの意味
4.3.2 単位体積のバルクの原子数密度
4.3.3 単位面積の表面に含まれる原子数
4.3.4 1nmの表面層に含まれる原子・分子数
4.4 表面,界面の重要性
4.4.1 表面処理の効果
4.4.2 表面,界面が関わる現象
4.4.3 表面,界面の効果
5. 分子間力の発現機構
5.1 自然界の4つの力
5.2 粒子間の相互作用
5.3 相互作用の理解に必要な基本概念
5.3.1 原子の構造
5.3.2 電子の軌道
5.3.3 クーロン相互作用(クーロン力)
5.3.4 相互作用のエネルギー表示と力表示
5.3.5 イオン化エネルギー
5.3.6 電子親和力
5.3.7 電気陰性度
5.3.8 極性分子と無極性分子
5.3.9 分極と双極子
5.3.10 分極率
5.4 化学結合
5.4.1 イオン結合
5.4.2 共有結合
5.4.3 金属結合
5.5 分子間力(分子間相互作用)
5.5.1 イオン間相互作用(点電荷-点電荷相互作用)
5.5.2 イオン-双極子相互作用(点電荷-双極子相互作用)
5.5.3 イオン-誘起双極子相互作用(点電荷-誘起双極子相互作用)
5.5.4 双極子-双極子相互作用(配向力)
5.5.5 双極子-誘起双極子相互作用(誘起力)
5.5.6 誘起双極子-誘起双極子相互作用(分散力)
5.5.7 交換斥力
5.5.8 レナード・ジョーンズ・ポテンシャル
5.5.9 水素結合
5.5.10 永久双極子の効果
5.5.11 分子間力に及ぼす重力の効果
6. 分子構造と親水性と疎水性
6.1 分子構造と親水性,疎水性の傾向
6.2 水
6.2.1 水分子の構造
6.2.2 水の性質
6.2.3 水和
6.3 アルカンとその関連物質
6.3.1 アルキル基
6.3.2 アルカン
6.3.3 ポリエチレン(PE)
6.3.4 ペルフルオロアルキル基,ペルフルオロアルカン
6.3.5 ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
6.4 ヒドロキシ基とアルコール
6.5 カルボキシ基と脂肪酸
6.6 疎水効果
6.7 その他の物質
6.7.1 石けん,界面活性剤
6.7.2 シリコーン
6.7.3 ガラス
7. 表面張力と表面自由エネルギー
7.1 表面張力
7.2 表面張力の起源
7.3 表面張力に影響する因子
7.3.1 分子間力
7.3.2 分子構造
7.3.3 分子の表面配向
7.3.4 水素結合
7.3.5 フッ素原子
7.4 表面張力の温度依存性
7.5 表面張力の定義
7.5.1 力としての表面張力
7.5.2 エネルギー的観点からの解釈 : 表面自由エネルギー
7.6 表面自由エネルギーと表面積
7.7 固体の表面張力,表面自由エネルギー
7.8 界面張力,界面自由エネルギー
7.9 付着・分離と表面自由エネルギー
7.9.1 界面における分離と付着仕事
7.9.2 Dupreの式
7.10 物質の大きさと表面張力
8. ラプラス圧
8.1 ラプラス圧のイメージ
8.2 界面におけるラプラス圧
8.3 毛管現象
8.4 Young-Laplaceの式
8.4.1 球面の場合
8.4.2 球状液膜の場合
8.4.3 任意の曲面の場合
8.4.4 円筒面の場合
8.4.5 液面の形状
9. 接触角と表面張力との関係
9.1 ぬれ性と接触角
9.2 接触角の定義
9.3 Youngの式
9.3.1 力のつり合いによる導出
9.3.2 熱力学によるYoungの式の導出
9.3.3 自由エネルギー極小点が平衡接触角になることの確認
9.4 臨界表面張力
9.4.1 Zismanプロット
9.4.2 臨界表面張力
9.5 ぬれの分類
9.5.1 状態の変化と自由エネルギー変化
9.5.2 付着ぬれ
9.5.3 Young-Dupreの式
9.5.4 拡張ぬれ
9.5.5 浸透ぬれ
9.5.6 浸漬ぬれ
9.6 ぬれ性を制御するための指針
10. ぬれ性と表面粗さ
10.1 表面粗さとぬれ
10.2 Wenzelの理論
10.3 Cassieの理論
10.3.1 複合面でのぬれ
10.3.2 Cassieの理論の粗面への応用
11. 静的ぬれと動的ぬれ
11.1 静的概念と動的概念
11.2 静的接触角と動的接触角
11.3 動的撥水性
11.4 静的表面張力と動的表面張力
12. 測定の一般的な注意点
12.1 測定値の信頼性
12.2 測定器の校正と調整
12.2.1 測定器の校正
12.2.2 測定器の調整
12.2.3 校正・調整のタイミング
12.2.4 測定標準の校正
12.2.5 校正・調整データの記録
12.3 測定値の確認と再測定
12.4 表面評価に関する注意点
12.5 器具類の洗浄に関する注意点
12.5.1 洗浄作業の流れ
12.5.2 ガラス製器具類の洗浄
12.5.3 すすぎ
12.5.4 共洗い
12.5.5 拭き取り
12.5.6 超音波洗浄
12.5.7 特定液体専用の注射器
12.5.8 ポリ袋やアルミホイルの利用
13. 接触角測定
13.1 接触角の解析方法
13.2 静的接触角の測定方法
13.2.1 液滴法
13.2.2 V-r法
13.2.3 そのほかの方法
13.3 動的接触角の測定方法
13.3.1 拡張収縮法
13.3.2 Wilhelmy法(垂直板法,プレート法)
13.3.3 滑落法(転落法)
13.3.4 動的撥水性の評価方法(動的滑落法)
13.4 接触角測定の特徴
13.5 接触角測定の注意点
13.5.1 接触角のばらつき
13.5.2 表面汚染の影響
13.5.3 表面帯電の影響
13.5.4 自重による潰れの影響
13.5.5 液量の影響
13.5.6 接触角解析方法の選択
14. 表面張力測定
14.1 表面張力の測定方法
14.1.1 Wilhelmy法(垂直板法,プレート法)
14.1.2 du Nouy法(輪環法,リング法)
14.1.3 懸滴法(ペンダントドロップ法)
14.1.4 最大泡圧法
14.2 表面張力測定の特徴
14.3 表面張力測定の注意点
15. 表面自由エネルギー解析
15.1 表面自由エネルギー解析の概要
15.2 表面自由エネルギー解析で何ができるか?
15.2.1 固体の表面張力の推定
15.2.2 表面自由エネルギー成分に基づく界面現象の理解
15.2.3 表面自由エネルギー成分に基づく材料設計
15.2.4 表面自由エネルギー解析の問題点
15.3 分子間力に基づく成分分けの概念
15.4 Fowkesの理論と検証
15.5 表面自由エネルギー成分分けの各種理論
15.5.1 Kaelble,Owens,北崎の理論
15.5.2 Wuの理論
15.5.3 酸-塩基理論
15.6 界面における相互作用
15.6.1 界面自由エネルギー
15.6.2 ぬれ性
15.6.3 付着仕事
15.7 固体の表面自由エネルギー成分の解析方法
15.8 プローブ液体の選択
15.8.1 プローブ液体の条件
15.8.2 Kaelble-Uyの理論で連立方程式を解くことの意味
15.8.3 接触角が解に及ぼす影響とプローブ液体の組み合わせとの関係
15.9 表面自由エネルギー解析による評価事例
15.10 表面自由エネルギー解析の注意点
15.10.1 解析理論の選択
15.10.2 表面自由エネルギーの成分数
15.10.3 プローブ液体の組み合わせの影響
15.10.4 プローブ液体のエネルギー値
15.10.5 液体のぬれ広がり
15.10.6 表面自由エネルギー解析の適用可否
16. 付録
16.1 熱力学
16.1.1 系,外界,孤立系
16.1.2 内部エネルギー
16.1.3 熱力学の第1法則(エネルギー保存則)
16.1.4 熱力学の第2法則(エントロピー増大則)
16.1.5 エントロピーの定義
16.1.6 自由エネルギー
16.1.7 自由エネルギーとは何が自由なのか
16.1.8 Helmholtzの自由エネルギーとGibbsの自由エネルギー
16.2 曲率と曲率半径
16.2.1 曲線の場合
16.2.2 曲面の場合
16.3 Young-Laplace曲線の導出
16.3.1 懸滴最下点OにおけるYoung-Laplaceの式
16.3.2 懸滴の輪郭曲線上の任意の点PにおけるYoung-Laplaceの式
16.3.3 懸滴の輪郭曲線の算出
16.3.4 静滴の輪郭曲線
16.4 ds/de法における補正係数1/Hの導出
参考文献/引用文献
索引
書籍コード:BC250901