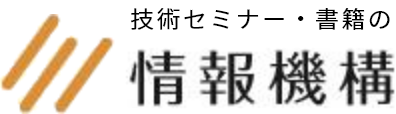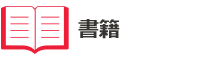早期割引
【早期割引にて申し込み受付中】 56,100円(税込(消費税10%)) 2024年6月24日まで
発刊・体裁・価格
発刊 2024年6月24日 定価 61,600円 (税込(消費税10%))
体裁 B5判 286ページ ISBN 978-4-86502-271-1 詳細、申込方法はこちらを参照
→書籍を購入された方へ(アンケートのお願い)
→PDFパンフレットを見る
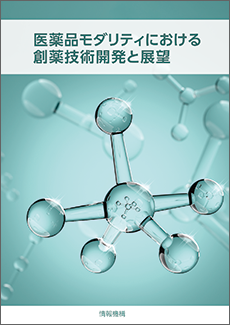
本書のポイント
●モダリティ技術・創薬技術で、幅広いジャンルの注目トピックスを掲載。…
〇日本・海外のモダリティライセンス状況やAIを使った技術開発など、
多面的に今の創薬技術開発の現状を理解できる。
【創薬モダリティの日本と海外のトピックスとは?】
>日本における技術トピックスの現状と今後の展望
>医薬品研究開発のオープンイノベーションとライセンス動向
>国別のライセンス状況
【低分子薬・中分子核酸医薬・バイオ創薬等の各分野での最新技術動向】
>RNAスプライシング、標的たんぱく質分解化合物、コパレント薬
>アンチセンス核酸医薬、デコイ型核酸医薬、核酸アプタマー医薬、分子ペプチド医薬
>ADC ( 抗体 - 薬物 ) 複合体、遺伝子治療薬
【注目されている各モダリティ技術の概要と技術開発の現状】
>mRNAデリバリー技術、エクソソーム、補体、老化細胞除去、セラノスティクス、天然物創薬ケミカルバイオロジー
【疾病別の治療・創薬技術開発の動向】
>血液がん治療、アルツハイマー型認知症、向精神薬開発、もやもや病、腎炎治療薬
【AIを利用した創薬技術開発の現在と展望】
>診療情報を利用したAI創薬、自然言語AI創薬標的探索研究
執筆者一覧(敬称略)
●辻真博((国研)科学技術振興機構)
●舩木美歩((国研)科学技術振興機構)
●網代将彦((国研)国立がん研究センター研究所)
●遠藤侑希(東京大学大学院)
●佐藤和佳(東京大学大学院)
●橋本創太(東京大学大学院)
●内藤幹彦(東京大学大学院)
●西山和宏(大阪公立大学大学院)
●西村明幸(自然科学研究機構)
●西田基宏(九州大学大学院/自然科学研究機構)
●笠原勇矢((国研)医薬基盤・健康・栄養研究所)
●三宅隆(大阪大学大学院)
●森下竜一(大阪大学大学院)
●坂本泰一(千葉工業大学)
●染谷龍彦(タグシクス・バイオ(株))
●堀美幸(タグシクス・バイオ(株))
●出水庸介(国立医薬品食品衛生研究所)
●眞鍋史乃(星薬科大学/東北大学)
●渡邊慶介((国研)国立がん研究センター)
●日比野沙奈((国研)国立がん研究センター)
●櫻井文教(近畿大学)
●持田祐希(東京医科歯科大学)
●内田智士(東京医科歯科大学)
●高橋有己(京都大学)
●植田康敬(大阪大学大学院)
●脇田将裕(大阪大学)
●原英二(大阪大学)
●上原知也(千葉大学)
●掛谷秀昭(京都大学大学院)
●夏目やよい((国研)医薬基盤・健康・栄養研究所)
●黒坂宗久(某国内製薬企業)
●山中聡士(愛媛大学)
●斎藤顕宜(東京理科大学)
●森戸大介(昭和大学)
●新妻邦泰(東北大学大学)
●遠田悦子(日本医科大学)
●寺島裕也(東京理科大学)
●和田学(中外製薬(株))
●近藤孝之(京都大学/理化学研究所)
●井上治久(京都大学/理化学研究所/京都大学医学部付属病院)
目次
第1章 創薬モダリティ技術と医薬品市場の概観
1.医薬品市場の概観
2.創薬モダリティ技術の概観
2.1 各創薬モダリティの技術的トピック
<低分子医薬 (20 世紀前半より市場形成 ) >
<タンパク・ペプチド医薬 ( 市場形成:1989 年~ ) >
<抗体医薬 ( 市場形成:1999 年~ ) >
<核酸医薬 ( 市場形成:2017 年~ ) >
<ex vivo 遺伝子治療 ( 市場形成:2020 年~ ) >
<in vivo 遺伝子治療 ( 市場形成:2021 年~ ) >
< mRNA ワクチン ( 市場形成:2021 年~ ) >
<細胞治療 [ 再生医療 ]( 市場形成:これから? )>
<ウイルス製剤治療、細菌製剤治療 ( 市場形成:これから? ) >
2.2 創薬モダリティ技術の横断的な分析
2.3 創薬モダリティ技術の評価系の展望
3.創薬における 3 つの柱 ( これから重要と思われる事項 )
3.1 創薬全般における重要事項
第2章 低分子創薬
第1節 RNA標的創薬技術開発の最先端:核酸医薬・低分子モダリティの進展
1.mRNAスプライシングを標的とした核酸医薬開発:ヌシネルセンとビルデプソ
1.1 脊髄性筋萎縮症 (spinal muscular atrophy;SMA) に対するヌシネルセンの開発
1.2 デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する核酸医薬開発
2.mRNAスプライシングを標的とした核酸医薬の開発:低分子化合物への展開
2.1 脊髄性筋萎縮症に対するリスジプラム
2.2 家族性自律神経失調症に対する開発化合物
2.3 CLK 阻害剤によるスプライシング標的治療の開発
3. mRNA標的型核酸医薬の開発展開
第2節 標的タンパク質分解を利用した医薬開発品
1.ユビキチン・プロテアソーム系タンパク質分解経路 (ubiquitin-proteasome system:UPS)
2.UPS を利用したタンパク質分解医薬品と PROTAC
3.SNIPER 技術について
3.1 IAP(Inhibitor of apoptosis)
3.2 SNIPER 開発への取り組み
4.PROTAC/SNIPER の課題
5.今後の展望
第3節 コパレント薬の概要と技術開発の現状
1.コバレントドラッグの歴史
2.最近のコバレントドラッグの紹介 ( 疾患別 )
2.1 悪性腫瘍を対象としたコバレントドラッグ
2.1.1 上皮成長因子受容体 (EGFR) 阻害剤
2.1.2 ブルトン型チロシンキナーゼ (BTK) 阻害剤
2.1.3 そのほかの標的
2.2 感染症を対象としたコバレントドラッグ
3.コバレントドラッグの新規ターゲットとしての GPCR
4.今後のコバレントドラッグの展開
4.1 新たな反応基の開発
4.2 他のモダリティ技術との融合
第3章 中分子核酸医薬
第1節 アンチセンス核酸医薬品創薬
1.アンチセンス核酸の分類
2.RNA分解型アンチセンス核酸の特徴と作用機序
3.スプライシング制御型アンチセンス核酸の特徴と作用機序
4.アンチセンス核酸に導入されている人工核酸
5.承認されているRNA分解型アンチセンス核酸
(1)Fomivirsen(商品名:Vitravene)
(2)Mipomersen(商品名:Kynamro)
(3)Inotersen(商品名:Tegsedi)
(4)Volanesorsen(商品名:Waylivra)
(5)Tofersen(商品名:Qalsody)
(6)Eplontersen(商品名:Wainua)
6.承認されているスプライシング制御型アンチセンス核酸
(1)Nusinersen(商品名:Spinraza)
(2)Eteplirsen(商品名:Exondys 51)
(3)Golodirsen(商品名:Vyondys 53)
(4)Viltolarsen(商品名:Viltepso)
(5)Casimersen(商品名:Amondys 45)
7.胃がん腹膜播種に対するRNA分解型アンチセンス核酸
第2節 デコイ型核酸医薬品の創薬開発
1.転写因子とデコイの作用機序
2.デコイの開発方針
3.適切な標的転写因子の探索
4.転写因子の選択とデコイの配列の決定
5.デコイの修飾と投与方法の決定
6.動物モデルで有効性の検討
7.デコイ療法の臨床試験
7.1 悪性腫瘍
7.2 心血管疾患
第3節 核酸アプタマー医薬品技術開発
1.アプタマーの作製法と特徴
1.1 アプタマーの作製法
1.1.1 SELEX 法
1.1.2 アプタマーの安定化
1.2 アプタマーの特徴
2.上市した核酸アプタマー医薬品
2.1 pegaptanib
2.2 avacincaptad pegol
3.臨床開発中のアプタマー
3.1 硝子体内投与 ―主に加齢黄斑変性症―
3.2 静脈内投与 ―循環器疾患関連―
3.3 皮下注射
4.今後の展望
第4節 中分子ペプチド医薬品開発
1.中分子ペプチド医薬品の開発動向
1.1 ペプチド医薬品の市場
1.2 ペプチド医薬品の特徴
2.β - カテニン標的阻害ペプチドの in silico デザイン
3.規制に関連する課題
第4章 バイオ創薬技術開発
第1節 ADC ( 抗体 - 薬物 ) 複合体の技術開発
1.抗体―薬物複合体の構造と作用機序
2.搭載薬物の種類
3.抗体の選択
4.リンカーの意義
4.1 構造
4.2 リンカーの重要性:搭載薬物の動態の制御
5.均一構造 ADC 作製の試み
5.1 Fc 結合ペプチドを用いた例
5.2 Fc に存在する糖鎖に搭載薬物を結合した例
6.新しい形の ADC
6.1 二重特異性抗体 ADC
6.2 Radioimmunotherapy
6.3 光免疫療法
第2節 CAR-T 細胞療法の現状と今後の展望
1.CAR-T 細胞療法とは
2.CAR の構造とその最適化
3.現行 CAR-T 細胞療法の問題点
3.1 再発・耐性化
3.2 有害事象とそのマネージメント
3.3 効果・再発予測のバイオマーカーの必要性
4.非 B 細胞性腫瘍に対する CAR-T 細胞療法の展開へ向けて-問題点とその克服-
4.1 固形腫瘍
4.1.1 標的抗原発現の不均一性
4.1.2 免疫抑制性の腫瘍微小環境
4.1.3 CAR-T 細胞の腫瘍局所への trafficking 不全
4.1.4 CAR-T 細胞の疲弊化
4.2 T 細胞性腫瘍
第3節 遺伝子治療薬の臨床開発の現状
1.遺伝子治療薬の臨床応用の現状
1.1 腫瘍溶解性ウイルス
1.2 ゲノム編集
2.遺伝子治療の最適化に向けた取り組み
3.安全性向上に向けた改良型 Ad ベクターの開発
4.遺伝子治療薬のレギュラトリーサイエンス
第5章 その他の創薬技術開発
第1節 mRNAデリバリー技術
1.治療用mRNAの設計
1.1 mRNAの構造単位と塩基
1.2 mRNAの部分構造とその役割
2.mRNA送達キャリア
2.1 mRNA送達キャリアの要件
2.1.1 キャリアの役割
2.1.2 細胞の種類ごとのデリバリー
2.1.3 リンパ節に対するデリバリー
2.1.4 脾臓に対するデリバリー
2.1.5 粘膜組織に対するデリバリー
2.1.6 がんに対するデリバリー
2.2 脂質ナノ粒子
2.3 ポリマーナノ粒子
2.4 将来の展望
第2節 エクソソームの概要と医療応用研究における現状
1.エクソソームの体内動態
2.天然のエクソソームを利用した治療法の開発
3.人工的に改変したエクソソームを利用した治療法の開発
第3節 補体を利用した治療薬技術開発
1.補体の体内における役割
1.1 補体とは
1.2 補体の活性化経路と作用
1.3 補体における自己・非自己の区別
1.4 補体制御因子
1.5 補体の体内における役割
2.補体の異常による疾患
2.1 補体関連疾患
3.補体の治療薬への応用手法
3.1 終末経路に作用
1) C5 阻害薬
①エクリズマブ (eculizumab, ソリリス R)
②ラブリズマブ (ravulizumab ,ALXN1210、ユルトミリス R)
④ポゼリマブ (pozelimab-bbfg、REGN3918、VeopozR)
⑤ジルコプラン (Zilucoplan、RA101495、ジルビスク R)
⑥ Cemdisiran (ALN-CC5)
⑦ Avacincaptad pegol (IZERVAY TM, Zimura R, ARC1905)
2) C5aR 阻害薬
①アバコパン (タブネオス R Avacopan, CCX168 )
② IFX-1 (vilobelimab , Gohibic R)
3) CD59 産生
① AAVCAGsCD59 (HMR59)
4) C3 阻害薬
①ペグセタコプラン (pegcetacoplan, APL-2 , エムパベリ R)
② AMY-101(Cp40
3.2 第二経路に作用
1) Factor D 阻害薬
①ダニコパン (Danicopan VoydeyaR)
②Vermicopan (ALXN2050)
③イプタコパン (Iptacopan、LNP023 , FabhaltaR)
3.3 古典経路に作用
※寒冷凝集素症 (Cold agglutinin disease:CAD)
1) C1s 阻害薬
①スチムリマブ (Sutimlimab、エンジャイモ R)
② SAR445088(BIVV020、Riliprubart)
③ ANX1502
2) C1q 阻害薬
① ANX005
② ANX007
3.4 レクチン経路に作用
1) MASP-2 阻害薬
①Narsopilimab (OMS721 )
4.補体研究のトピックス
1) 自然免疫以外の役割
2) 細胞内補体
5.今後の抗補体薬の課題
1) 補体の病態への関与の程度
2) 完全な阻止か、制御か
3) 局所での制御
第4節 老化細胞除去 ( セノセラピー ) の技術開発
1.細胞老化について
1.1 細胞老化とその生理的意義
1.2 高齢化社会における細胞老化の生理的意義
2.治療標的としての老化細胞
2.1 老化細胞の特徴
2.2 治療標的としての老化細胞の可能性
3.老化細胞除去法 ( セノセラピー ) の開発
3.1 セノセラピーの概要
3.2 セノリティックドラッグ ( 老化細胞除去薬 ) の開発
3.3 老化細胞を標的とする免疫療法
3.4 セノモルフィリックドラッグ (SASP 調節薬 ) の開発
第5節 セラノスティクス技術開発
1.セラノスティクスとは
2.現在使用されているラジオセラノスティクス薬剤
3.今後期待されるラジオセラノスティクス薬剤
4.核医学領域以外の展開
第6節 医薬品モダリティの開発を指向した天然物創薬ケミカルバイオロジー
1.医薬品の起源と疾病
2.希少放線菌Saccharothrix sp.A1506 株が生産する新規抗がん剤
Saccharothriolide 類
3.革新的プロドラッグ型クルクミン CMG 及び TBP1901 の開発
第7節 診療情報を利用した AI 創薬技術開発
1.診療情報を利用した AI 創薬の現状
2.診療情報を利用した AI 創薬の課題
3.世界の動向、日本の動向、そしてバイオバンクの役割
4.今後の展望
第6章ディール分析によるモダリティのインライセンス動向と展望
1.世界の医薬品市場動向
1.1 モダリティ別の世界の医薬品市場
1.2 上市された新規医薬品のモダリティ
2.医薬品研究開発のオープンイノベーションとライセンス動向
2.1 世界のライセンス市場の概要
2.2 モダリティ別の製品導入 ( ライセンス ) トレンド
2.3 国別のライセンス状況
3.創薬ベンチャーのトレンドについて
3.1 ベンチャーファイナンス市場の概要
3.2 創業企業が扱うモダリティ
3.3 ベンチャー投資されるモダリティ
第7章各疾患における創薬研究
第1節 催奇性を軽減した血液がん治療に有効な新規サリドマイド誘導体の開発
1.サリドマイドやサリドマイド誘導体の作用メカニズム
2.催奇性を軽減した新規サリドマイド誘導体の開発
2.1 サリドマイド誘導体に関する薬剤研究の現状
2.2 サリドマイド誘導体におけるネオ基質選択性の概要と薬剤への応用
2.3 サリドマイド誘導体依存的な相互作用解析技術の開発
2.4 催奇性を軽減した血液がんに有効な新規サリドマイド誘導体の同定
3.キメラ型タンパク質分解薬への応用
第2節 iPS 細胞を用いたアルツハイマー型認知症の創薬標的の研究開発
1.アルツハイマー病の病態
2.アルツハイマー病の iPS 細胞モデル
3.iPS 細胞を用いたアルツハイマー病の治療法開発
第3節 オピオイド受容体を標的とした向精神薬の研究開発
1.DOR 作動薬による治療概念 (Proof of concept:POC) の実証
1.1 DOR 作動薬による抗うつ様作用・抗不安様作用の発見
1.2 痙攣作用のない DOR 作動薬の発見
1.3 既存薬との差別化
2.DOR の治療効果に対する作用機序 (Proof of mechanism:POM) の実証
2.1 PL-PFC の DOR を介した生得的不安の制御機構
2.2 IL-PFC の DOR を介した恐怖記憶の制御機構
2.3 海馬DOR を介した抗ストレス効果
3.DOR 作動薬の臨床開発状況
4.今後の展望
第4節 もやもや病の発病メカニズムと創薬研究開発
1.もやもや病の臨床像
2.現行の治療とアンメットメディカルニーズ
3.責任遺伝子と分子病態
4.もやもや病創薬の現状と可能性
第5節 マクロファージの動きと活性化を調節する腎炎治療薬開発
1.様々な腎疾患とマクロファージの関与
2.マクロファージを標的とした治療
3.FROUNT を介してマクロファージを制御する新たなアプローチ
第8章 自然言語 AIを活用した創薬標的探索研究開発
1.AI の活用場面とは
2.論文検索/探索における自然言語 AI の活用
3.機械学習による標的予測
4.知識グラフと標的探索
5.LLM /生成 AI と仮説生成