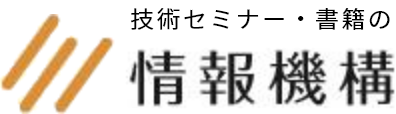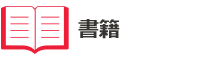著者
中原 武 著
島根県立出雲産業高校工業化学科卒業後、(株)日立製作所入社
日立茨城工業専門学校化学工学科卒業後、東京大学理学部化学科島内研究室研究生(構造化学)
日立化成工業(株)復職後、HN-2200、HN-5500、HN-7000他の液状酸無水物系エポキシ樹脂硬化剤の研究開発及び市場開拓を行う。
その間、エポキシ樹脂技術協会の試験規格委員会で、エポキシ樹脂及び酸無水物系硬化剤等のJIS及びISO規格の制定を行う。
日立化成工業(株)を定年退職後、(株)寺田でアミン系硬化剤を使用したエポキシ樹脂コンパウンドの開発を行う。
<主な著書>
・新保正樹編「エポキシ樹脂ハンドブック」、179~209ページの「酸および酸無水物系硬化剤」、日刊工業新聞社(1987年)
・「エポキシ樹脂の高機能化と硬化剤の配合技術および評価、応用」、117~129ページの「酸無水物系硬化剤」、技術情報協会(1997年)
・「電材ジャーナル」、第612号、34~38ページの「電気用エポキシ樹脂硬化剤の歴史」、電気機能材料工業会(2011年)
発刊・体裁・価格
発刊 2018年7月9日 定価 48,400円 (税込(消費税10%))
体裁 A4判 427ページ ISBN 978-4-86502-151-6 →詳細、申込方法はこちらを参照
→書籍を購入された方へ(アンケートのお願い)
→PDFパンフレットを見る
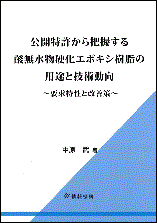
はじめにより抜粋
1993年に青色発光ダイオードが(LED)が開発され、交通信号や家庭用照明に至るまで用途が拡大し、酸無水物系硬化剤需要の飛躍的上昇をもたらした。筆者らは、1980年にHN-5500、2003年にHN-7000を開発し、LEDへの需要に対応してきた。
本書は、1993年1月~2018年1月末までの26年間の公開特許公報から、酸無水物系エポキシ樹脂硬化剤を使用した特許を選び、独自に用途別に分類して、その技術的進歩をまとめたものである。
また、併せてこの間に公示された新規なエポキシ樹脂、酸無水物系硬化剤、及び硬化促進剤をはじめ、硬化方法や酸無水物硬化樹脂のリサイクル等についてもまとめてみた。
なお、特許公報の検索は、特許庁の特許情報プラットフォームを使用させていただいた。公開特許のうち、2018年3月1日時点で特許登録されたものは、公開特許番号の下に登録番号を併記した。
また、本書の主題である「公開特許から把握する酸無水物硬化エポキシ樹脂の用途と技術動向」は、その後特許登録されたものを中心に説明を加えた。
目次
【1】光半導体、光学用樹脂における要求特性と、課題解決に向けた技術動向
1.1 LED用液状封止材~硬化物の無色透明性が必須で変色防止への対応1
1.1.1 エポキシ樹脂~高輝度及び短波長LEDへの対応など
1.1.2 酸無水物系及びカルボン酸系硬化剤~表面実装型LEDへの対応など
1.1.3 硬化促進剤及び添加剤~変色防止、薄膜硬化、短波長化対応など
1.1.4 低応力化、耐クラック性及び耐光性の改良~シリカ微粒子、カップリング剤、シリコーン樹脂粒子、ゴム粒子等の添加など
1.2 LED用モールド封止材~無色透明性、耐熱性、量産性など
1.2.1 エポキシ樹脂及びプレポリマー~速硬化、耐クラック性、低応力性
1.2.2 硬化剤~Bステージ状態の安定化、高耐熱性化など
1.2.3 硬化促進剤~速硬化性、紫外線領域までの光透過性など
1.2.4 離型剤~透明性と離形性の両立
1.2.5 低応力化、耐クラック性の改良~アルコールやガラス粉末の添加など
1.3 LEDパッケージ用モールド樹脂~熱可塑性樹脂からエポキシ樹脂へ移行
1.3.1 エポキシ樹脂及びプレポリマー~耐熱耐光性や耐クラック性向上
1.3.2 硬化剤~酸無水物及び多価カルボン酸縮合体など
1.3.3 硬化促進剤~ホスホニウム塩など
1.3.4 充填剤及び白色顔料~熱伝導性、光反射特性を考慮して選択
1.3.5 添加剤~バリ及びクラックの抑制、酸化防止剤、離型剤
1.4 液晶表示素子用透明基板~割れにくく軽量化や薄型化が可能な基板
1.4.1 注型法による製造~耐熱性、無色透明性、ガスバリア性など
1.4.2 流涎成形法による製造~厚み均一化のため粘度調整など
1.4.3 積層成形法による製造~屈折率差が小さく表面平滑性に優れた基板
1.5 光学用エポキシ樹脂組成物~低屈折率樹脂、偏光板の接着剤など
【2】半導体用樹脂における要求特性と技術動向
2.1 モールド封止材~小型化、薄型化、配線間隔の狭小化への対応など
2.1.1 トランスファ成形用封止材~ウエハレベルCSP用封止材など
2.1.2 圧縮成形用封止材~反り抑制のため充填剤を高充填など
2.1.3 フイルム状封止材~ウエハレベルパッケージに好適な最新技術
2.2 液状封止材~表面実装対応封止材、アンダーフィル材など
2.2.1 COB用液状封止材~耐湿性及び耐ハンダクラック性の向上など
2.2.2 フリップチップ用液状封止材(アンダーフィル材)~侵入性、フィレット性、速硬化性、耐湿信頼性などへの対応
(1)フリップチップ実装方法
(2)ディスペンサ等による注入用封止材
(3)印刷等によるリフロー同時封止材及びノンフロー封止材
2.2.3 COF用液状封止材(アンダーフィル材)~マイグレーション抑制、狭ピッチ化に伴うアンダーフィル材の剥離やクラックの抑制など
2.3 一液性エポキシ樹脂組成物とその用途~新規潜在性触媒など
2.3.1 潜在性硬化促進剤及び潜在性硬化剤~エポキシ樹脂や酸無水物に可溶であるが、低温で長ポットライフ、高温で速硬化する触媒など
2.3.2 半導体用一液性エポキシ樹脂~アンダーフィル材の低弾性率化など
2.3.3 電気・電子部品用一液性エポキシ樹脂~コンデンサや絶縁コイル用など
2.3.4 接着剤用一液性エポキシ樹脂~モータマグネット用や液晶シール材
【3】重電注型、含浸用樹脂における要求特性と課題解決に向けた技術動向
3.1 重電注型用樹脂~機械強度や靱性及び耐クラック性の向上など
3.2 高電圧機器用モールド樹脂~熱伝導率の向上、充填剤の沈降量低減、耐クラック性の付与、高靱性高熱伝導性組成物など
3.3 ガス絶縁機器用注型樹脂~低誘電率で作業性良好なスペーサー用樹脂など
3.4 加圧ゲル化用樹脂~屋外用ボイドレス成形品やモールドコイル製造用など
3.5 重電含浸用樹脂
3.5.1 回転機の含浸用樹脂~耐熱性や接着性と靱性付与、ワニスの流失防止とポットライフの向上など
3.5.2 回転機の全含浸用樹脂~保存安定性と薄膜硬化性、ワニスの流出を防止するマイカテープ、絶縁システムの高耐熱化法など
3.5.3 含浸用一液型エポキシ樹脂~金属アセチルアセトネートの溶解法など
3.5.4 超電導マグネットコイルの含浸用樹脂~クエンチ対策
3.5.5 回転機の滴下含浸用樹脂~耐熱性200℃以上の組成物
3.5.6 車両用リアクトルの含浸用樹脂~含浸樹脂の流出抑制
【4】電気電子部品用樹脂における要求特性とそれに応じた樹脂組成物の技術動向
4.1 コイル、トランス注型用樹脂~充填剤の沈降抑制、樹脂粘度の最適化など
4.2 電気・電子部品注型、封止用樹脂~注入作業性/耐クラック性/耐熱性等への要求対応な
4.3 コンデンサ含浸、注型用樹脂~含浸性/耐熱性/耐湿性への要求対応など
4.4 液状樹脂の射出成形~成形品の内部応力低減対応など
4.5 導電性樹脂~銀ペースト、導電性接着剤、導電性樹脂シートなど
4.6 異方性導電材料~配線パターンの狭小化への対応、高温高湿下での耐衝撃性/導通信頼性の向上など
4.7 接着剤、接着テープ~ダイボンド剤、熱応力緩和、接着耐久性の向上、フラックス不要ハンダバンプ接合接着剤など
4.8 エポキシ樹脂フイルム~LCD/有機EL用基板、耐熱黄変性薄膜など
4.9 その他電気・電子部品用樹脂~磁気ヘッド、サーミスタ用樹脂など
【5】FRP、積層板用樹脂の要求特性と課題解決に向けた技術動向
5.1 FRP、CFRP用樹脂~低粘度/伸度と耐熱性とのバランス、含浸性/接着強度向上界面活性剤、振動/音/衝撃を吸収・減衰するFRP用樹脂など
5.2 引き抜き成形用樹脂~エポキシ基含有ビニルエステル樹脂、内部離型剤など
5.3 積層板、プリント配線板用樹脂
5.3.1 プリント配線板の難燃化~HCA誘導体、耐湿性耐熱性の改良など
5.3.2 プリント配線板~弾性率の向上、高周波対応樹脂、LED実装用など
5.3.3 多層プリント配線板~耐熱性接着剤付き銅箔、層間絶縁接着剤など
5.3.4 熱伝導(放熱性)基板~熱伝導体と導電層接着用絶縁シートなど
5.3.5 プリント配線板のソルダーレジスト~保存安定性と解像性など
【6】その多用途における要求特性と課題解決に向けた技術動向
6.1 粉体塗料用樹脂~鋳鉄管内面塗料、電気・電子部品被覆塗料など
6.2 人造大理石用樹脂~着色が少なく良好な白色度を有する組成物など
6.3 樹脂型用エポキシ樹脂~低収縮率/高熱伝導率、離型性/転写性など
6.4 樹脂結合型希土類磁石~小型モータ用磁石など
6.5 ガス分離膜モジュール~耐熱性/耐圧性/耐クラック性の管板
【7】エポキシ樹脂の技術的進歩と技術動向
7.1 新規なエポキシ樹脂~耐熱性/低線膨張係数/相溶性改良、接着強度/耐熱性/高温での曲げ特性に優れた新規エポキシ樹脂など
7.2 水添エポキシ樹脂~靱性/耐クラック性改良、LED封止材用など
7.3 エポキシシリコーン樹脂~アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂、硬度/強度/耐熱耐UV性に優れたエポキシシリコーン樹脂など
【8】酸無水物、促進剤、添加剤の技術的進歩と技術動向
8.1 新規酸無水物~メチレンノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水物及びその水素化物、末端に酸無水物基を有するイミド系オリゴマーなど
8.2 多塩基酸無水物~低融点で作業性の優れたMNTC及びその水素化物、トリメリット酸エステルのテトラカルボン酸無水物など
8.3 酸無水物と促進剤orエポキシ樹脂混合物~貯蔵安定性の向上策、炭酸ガスやひけの発生が少ない組成物など
8.4 硬化促進剤~中温硬化、加圧ゲル化用硬化促進剤、潜在性硬化促進剤など
8.5 潜在性触媒~テトラフェニルホスホニウムボレート及びホスホニウムボレート塩、トリアリールボラン-アミン錯体など
8.6 添加剤~マレイミド化合物、エチレン共重合体アイオノマーなど
【9】硬化方法の技術的進歩と技術動向
9.1 酸無水物硬化+ラジカル重合併用系~配線板の薄型化に伴う反りを防止、オーバーコート材の密着性改良など
9.2 エネルギー線硬化~硬化能力が高い高硬化性樹脂組成物
【10】その他
10.1 酸無水物硬化樹脂のリサイクル~炭素繊維/エポキシ樹脂複合材料から炭素繊維の回収など
10.2 分解性エポキシ樹脂~初期接着性に優れ不要になった時にエネルギー線照射等により剥離して基材を回収できる接着剤など