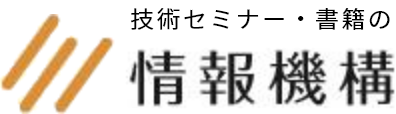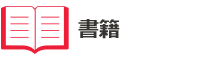早期割引
【早期割引にて申し込み受付中】 55,000円(税込(消費税10%)) 2025年5月27日まで
発刊・体裁・価格
発刊 2025年4月24日 定価 59,400円 (税込(消費税10%))
体裁 B5判 200ページ ISBN 978-4-86502-285-8 →詳細、申込方法はこちらを参照
→書籍を購入された方へ(アンケートのお願い)
→PDFパンフレットを見る
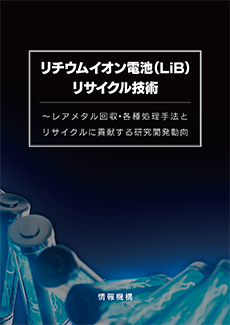
本書のポイント
★レアメタルの地政学リスク、EVの出口戦略...様々な問題を背景に注目集めるリチウムイオン電池(LiB)のリサイクル技術!
★関連法規とビジネス動向、電池中のレアメタル回収技術をはじめ、リサイクルにおける各種処理と安全対策、
必要な分析評価手法からリサイクルに貢献する部材開発事例まで網羅!
〇ビジネス動向と関連法規
・鉱産,自動車,電池メーカーなど国内外の関係企業の動き、3R法,バーゼル法などの関連法規と業界対応
・欧州、中国、米国でのEVバッテリーリサイクルの動き
・国内外の電池生産量、中古LiBの流通状況、ビジネスの可能性について
〇レアメタルの回収技術
・代表的な処理フロー解説(ダイレクトリサイクル法、乾式精錬法、湿式精錬法)、リサイクルのコスト構造
・ニッケル,コバルト,リチウム,ふっ素の分離回収技術、物理選別や元素分離技術
〇リサイクルを安全に行うための処理技術
・環境負荷の少ない処理手法、電極活物質にダメージを与えない回収方法、発火事故原因と対策
〇リサイクルにおいて必要な検出・分析評価技術
・廃棄物中のバッテリー検出、不純物評価、純度の考え方、結晶構造解析、有機物分析、
部材の物性評価などの各種分析手法と分析結果例
〇リサイクルに貢献する部材開発
・バインダー設計指針と溶出方法、レアメタルのバイオ吸着剤、安全性とリサイクル効率を考慮したバッテリパック設計、
ふっ素フリー水系バインダー開発
執筆者一覧(敬称略)
菅原秀一(泉化研)
沖本真也(沖為工作室合同会社)
福代和宏(山口大学)
熊谷誠治(秋田大学)
安部勇輔(秋田大学)
青野宏通(愛媛大学)
近藤治郎((株)イージーエス)
佐々木一哉(弘前大学)
森良平(GSアライアンス(株))
高谷雄太郎(東京大学)
所千晴(早稲田大学)
齋藤優子(東北大学)
森田宜典(DOWAエコシステム(株))
熊谷将吾(東北大学)
白鳥寿一(東北大学)
吉岡敏明(東北大学)
寺門修(函館工業高等専門学校)
葛原俊介(仙台高等専門学校)
粕谷亮(産業技術総合研究所)
渡邉賢(東北大学)
松本太(神奈川大学)
福西美香(神奈川大学)
鹿島理((株)GSユアサ)
上田高生(産業技術総合研究所)
速水弘子(日鉄テクノロジー(株))
小西康裕(大阪公立大学)
髙瀨弘嗣(デルタテックラボラトリ(株))
清水義久(東ソー(株))
目次
第1章 リチウムイオン電池リサイクルにおける国内外の関連法規制と市場動向
第1節 国内外におけるEV バッテリーのリサイクル動向
1.今後の電池GWh 数、グローバル2030 と2035
2.リサイクルに関する国内外の企業動向
3.国内の関連法規制と業界対応、3R 法とバーゼル法ほか
4.EU 電池規制と元素リサイクル、回収目標と電池パスポート
5.リサイクルの流れの構築、ハブ方式と独立方式
第2節 車載バッテリーリサイクルに関わる動向―欧州、中国、米国の動き―
1.市場概観
2.欧州の動き
3.中国の動き
4.米国の動き
5.まとめ
第3節 LiB リサイクルのビジネス動向と可能性
1.国内外での電池生産量
2.中古LiB の国内流通状況
3.リサイクルビジネスの動向と可能性
第2章 レアメタル回収技術・各種処理手法および安全対策
第1節 LiB リサイクルの主要フローと処理手法比較
1.LiB リサイクルプロセスの全体像
1.1 リサイクルの主要フロー
1.2 LiB の回収
1.3 LiB の解体
2.狭義のリサイクル
2.1 多様なリサイクル手法
2.2 乾式精錬
2.3 湿式精錬(予備処理)
2.4 湿式精錬(浸出から分離まで)
2.5 その他のリサイクル手法
3.リサイクルの収益性
3.1 リサイクルのコスト構造
3.2 湿式精錬のコスト
3.3 リサイクルの収益性に関するまとめ
第2節 電極材料のリサイクル技術と国内外の動向
1. LiB リサイクルの需要
1.1 LiB の構成材料
1.2 電極材料の将来需要
1.3 LiB 排出量の見込み
2. LiB 電極材料のリサイクル技術
2.1 ダイレクトリサイクル法
2.2 乾式精錬法
2.3 湿式精錬法
2.4 国内における現在主流のリサイクルプロセス
2.5 負極材のリサイクル
3. 国内外におけるLiB 正極材リサイクル技術の動向
3.1 住友金属鉱山・関東電化工業の正極材リサイクル
3.2 JX 金属サーキュラーソリューションズの正極材リサイクル
3.3 JERA・住友化学の正極材リサイクル
3.4 DOWA の正極材リサイクル
3.5 三菱マテリアル・エンビプロ・VOLTA の正極材リサイクル
3.6 Umicore(ベルギー)の正極材リサイクル
3.7 Ascend Elements(米国)の正極材リサイクル
4. LiB 正極材リサイクルの将来展望
第3節 レアメタル回収技術
第1項 使用済みLiBからのイオン交換樹脂によるNi、Co 等の分離回収技術
1.はじめに
2.車載用使用済みLIBの処理
3.ブラックサンド中のNi、Co 資源評価
4.Ni、Co の分離回収
5.使用済みLiBからのレアメタル等回収モデル
6.今後の展望
第2項 高純度Li回収技術
1.リチウム回収の背景
1.1 リチウム資源の重要性
1.2 リチウム資源獲得に向けた世界の動向
1.3 リチウムリサイクル市場規模の見通し
2. 廃LIBsリサイクルに関するバリューチェーンの概要
2.1 バリューチェーンの概要
2.2 LIBsの国内生産へのシフト
3. 廃LIBsのリサイクル工程
3.1 収集・運搬
3.2 前処理(放電・解体・分解)
3.3 BM 製造
3.4 Li 回収・精製・化合物化
4. 代表的なLi 抽出方法
4.1 沈殿法
4.2 吸着法
4.3 溶媒抽出法
4.4 膜分離法
4.5 電気透析法
4.5.1 電気透析によるLi 回収の機構と特徴
4.5.2 リチウム化合物の純度
4.5.3 Li 回収速度とエネルギー効率
第3項 ブラックマスからのレアメタル金属回収と再生型リチウムイオン電池の作成
1. ブラックマスの化学組成
2. 深共晶溶媒とは
3. 深共晶溶媒によるコバルト酸リチウム、ブラックマスからのコバルト抽出
4. ブラックマスから直接作成する再生型リチウムイオン電池の開発
第4項 LiBの分離濃縮技術~物理選別・各元素の分離技術
1. 廃LiB処理プロセスの概要
2. 物理選別によるブラックマス回収と湿式処理による各元素の分離
3. ダイレクトリサイクル実現に向けた取り組み – 最新の研究事例紹介–
3.1 電気パルス放電処理によるAl集電箔と正極活物質の高度分離
3.2 活物質再生に関する新しい取り組み(還元硫化焙焼と活物質再生)
4. まとめと今後の展望
第5項 フッ素回収を目的とした小型電気電子機器由来リチウムイオン電池の不活性化
1. LiBにおけるフッ素樹脂の局在
2. 減圧加熱によるリチウムイオン電池不活性化の検討
3. 使用済み小型電気電子機器由来LiB回収の意義
第6項 リチウムイオン二次電池の持続的リサイクルに向けたフッ素回収
1. PVDF熱分解によるHFの発生挙動
2. カルシウム化合物によるPVDF由来Fの固定化
第4節 高温高圧流体を利用したLIB再生に関する技術
1. リチウムイオン電池(LIB)の需要と資源問題
2. リチウムイオン電池(LIB)リサイクル
3. 湿式精錬の現状と当研究室での水熱酸浸出に関する取り組み
4. 水熱および超臨界流体技術によるLIBリサイクル適用技術
第5節 リサイクルされた電極活物質の再利用のための処理方法
1. 使用された電極からの電極活物質の回収
1.1 熱処理による回収
1.2 バインダーの溶解による回収
2. 回収された電極活物質の再利用のための処理法
2.1 使用済み正極活物質の再生法
2.1.1 固体焼結法
2.1.2 共晶溶融塩法
2.1.3 水熱法
2.1.4 化学反応によるLiドープ法
2.1.5 電気化学法を用いたLiドープ法
2.1.6 各再生法の長所と短所
2.2 使用済み負極活物質の再生法
3. まとめ
第6節 リサイクル現場における発火事故の実態と対策等の取組
1. 製品市場で起きている事故の実態
1.1 消費者庁による事故の概要
1.2 NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)による事故情報
1.3 LIB による火災の発生状況
2. リサイクル施設で起きている事故の実態
2.1 リサイクル施設での事故実態
2.1.1 日本容器包装リサイクル協会の事例
2.1.2 環境省による調査結果
2.1.3 発火事故事例に関する調査報告
2.2 発火事故による損害
3. リサイクル施設における事故対策
4. 処理中の事故の発生原因
4.1 事故の推定原因
4.2 消費者が排出しやすい回収ルートの整備
4.3 消費者が適切に分別するための情報発信
5. 制度の施行状況と課題
第3章 リサイクル時に必要な各種評価
第1節 リサイクル施設における廃棄物に紛れたバッテリーの自動検出
1. 透過X 線及び深層学習によるバッテリー検出の基礎検討
2. バッテリー検出プログラムの開発
3. 検出性能の検証
4. 概念実証用システムの開発
5. 社会実装に向けた取り組み
第2節 リサイクルにおける分析評価技術
1. LiB リサイクルにおいて必要な分析評価技術
2. リサイクルにおいて基本となる分析評価技術
2.1 無機分析(化学組成および不純物評価)
2.1.1 XRF による組成、不純物分析
2.1.2 ICP-OES による組成、不純物分析
2.1.3 ICP-MS による不純物分析
2.1.4 その他の無機分析
2.2 XRD 分析およびXAFS 分析による構造解析
2.3 ラマン分光分析
2.4 有機物分析
2.5 表面化学状態分析
3. 電池部材の物性評価
3.1 BET 比表面積/ 細孔分布測定
3.2 熱伝導率測定
3.3 熱分析(DSC およびTG-DTA)
3.4 粉末の形状測定
4. その他必要となる分析評価技術
4.1 SAICAS 法(分析面出し、みなしせん断強度、剥離強度などの膜特性評価)
4.2 発生ガス成分リアルタイム分析
第4章 リサイクルに貢献する部材の設計・開発技術
第1節 リサイクルのためのバインダー設計および電極からのバインダーの溶出
1. 水系バインダー
2. 電子伝導性バインダー
3. 天然由来のバインダー
4. PVDF 溶媒
5. まとめ
第2節 バイオ分離剤の開発とLiB リサイクルへの適用検討
1. バイオ浸出方法とその適用
1.1 バイオ分離剤シワネラ属細菌とマンガン酸化物のバイオ浸出機構
1.2 マンガン系電池正極材料のバイオ浸出
1.2.1 使用済みアルカリ電池
1.2.2 電池正極材マンガン酸リチウム
2. バイオ吸着方法とその適用
2.1 バイオ分離剤パン酵母とレアメタルのバイオ吸着機構
2.2 コバルトおよびニッケルのバイオ吸着
第3節 安全性とリサイクル性を両立するバッテリパック設計
1. バッテリパック設計の基本
1.1 バッテリパックの構成要素
1.2 バッテリパック設計の基本要件
1.3 リサイクル規制の影響
1.4 バッテリパック設計の今後
2. リサイクルを考慮した設計アプローチ
2.1 モジュール化設計
2.2 材料選定の工夫
2.3 分解性への配慮
2.4 安全性への配慮
2.5 デジタルツインによる設計最適化
3. リサイクル規制とバッテリパック設計への影響
3.1 リサイクル規制の概要
3.1.1 EU のバッテリ規則
3.1.2 中国のバッテリリサイクル規制
3.1.3 米国のバッテリリサイクル規制
3.2 バッテリパック設計に対する具体的な影響
3.3 規制強化による今後の課題
第4節 ふっ素フリー水系バインダー開発
1. 従来品の課題と本開発の意義
1.1 背景
1.2 正極用活物質
1.3 バインダー材料に対するニーズ
1.4 従来品の課題と本開発の意義
2. ふっ素フリー水系材料の開発、設計コンセプト
2.1 耐酸化性
2.2 マンガンの捕捉機能
2.3 環境対応設計(ふっ素フリー、水系材料)
3. 性能評価方法など
3.1 Mn の捕捉試験
3.2 電池の性能評価
3.2.1 電池の作製条件
3.2.2 電池の性能評価
4. 開発品の特長
4.1 高温でのサイクル容量維持率
4.2 交流インピーダンス