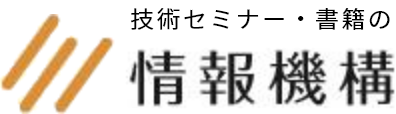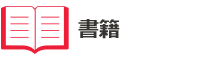発刊・体裁・価格
発刊 2010年3月26日 定価 10,450円 (税込(消費税10%))
体裁 B5判 220ページ ISBN 978-4-904080-49-8 →詳細、申込方法はこちらを参照
→書籍を購入された方へ(アンケートのお願い)
→PDFパンフレットを見る
執筆者一覧(敬称略)
●富樫 盛典 (株)日立製作所
●遠藤 喜重 (株)日立プラントテクノロジー
●三宅 亮 (広島大学)
こんなことが理解できます
○マイクロリアクタの特徴と適用可能なプロセス
○マイクロリアクタの実験方法とシミュレーション技術
○マイクロリアクタによるプロセス革新と環境負荷低減の具体的な事例
○マイクロリアクタのプラント化
本書のポイント
具体的な適用例、開発事例を記載!
化学反応を行うためのマイクロデバイスはマイクロリアクタと呼ばれているが、その流路幅は髪の毛の断面ぐらい、つまり数10~100μm程度である。
マイクロリアクタは、従来の撹拌槽方式バッチ法を用いた化学反応に比べて、マイクロメータのレベルで高速かつ均一に混合・反応が起こる。そのため、飛躍的なプロセス革新(収率向上、品質向上、連続フロー処理、スピードアップ)と環境負荷低減(廃棄物低減や省エネ)を実現する事ができ、従来の各種プロセスを大きく変えようとしている。
本書では、マイクロリアクタの基礎と実験および適用のポイント、最新開発動向を始め、プロセス向上と環境負荷低減の適用事例を示す。さらに量産を見据えたナンバリングアップによる実証プラント化の動向についてもわかりやすく解説してある。
マイクロリアクタの導入を検討されているビギナーの方から、量産プラント化を考えておられるエキスパートの方まで、幅広い研究者および技術者の方々に役立てば幸いである。
◎マイクロリアクタ特徴
・マイクロ化のメリット・デメリットとは?
・実験の方法を詳細に解説!
実験装置の構成、圧力損失・滞留時間の見積もり、
・マイクロリアクタの適用が可能なプロセスとは?
◎マイクロリアクタの最新開発動向
・マイクロリアクタのニーズ調査とは?
利用可能なプロセス・利用で重視する仕様・性能
・ニーズ、市場規模とは?
◎各種プロセスを徹底解明!
・液相反応、ナノ粒子生成、乳化、液液抽出および濃縮プロセスなど。
◎シュミレーション活用による予測技術
・モンテカルロ法、分子移動の法則など。
◎マイクロリアクタのプラント化
・プラント化に実例・・・外部ナンバリングアップ方式、内部ナンバリングアップ方式のプラントとは?
目次
第1章 マイクロリアクタの基礎
1.マイクロリアクタの特徴と種類
1.1 マイクロリアクタとは
1.2 マイクロリアクタの特徴
1.3 マイクロリアクタの種類
1.3.1 構造による分類
1.3.2 用途による分類
1.3.3 材質による分類
2.マイクロ化のメリット・デメリット
2.1 マイクロ流体の基礎
2.1.1 流体の基礎方程式
2.1.2 無次元数
2.1.3 寸法効果
2.2 マイクロ化のメリット
2.2.1 拡散方程式
2.2.2 拡散係数
2.2.3 分子拡散・温度拡散の寸法効果
2.2.4 反応時間短縮・収率向上
2.2.5 生産物質の品質向上
2.3 マイクロ化のデメリット
2.3.1 ハーゲン・ポアズイユの式
2.3.2 圧力損失の寸法効果
2.3.3 表面張力の寸法効果
3.マイクロリアクタ実験の方法
3.1 実験装置の構成
3.2 圧力損失の見積もり
3.3 滞留時間の見積もり
3.4 流路内の気泡除去の方法
3.5 ラボ用のマイクロリアクタシステム
4.マイクロリアクタの適用が可能なプロセス
第2章 マイクロリアクタの作製方法
1.流路の加工方法
1.1 機械による除去加工
1.2 半導体プロセス利用による加工
1.2.1 エッチング方法の分類
1.2.2 等方性および異方性エッチング
1.2.3 ウェットエッチング
1.2.4 ドライエッチング
2.接合方法
2.1 接合方法の分類
2.2 拡散接合
2.3 陽極接合
第3章 マイクロリアクタの開発動向
1.マイクロリアクタのニーズ調査
1.1 利用可能な技術領域
1.2 重視する仕様・性能
2.海外の開発動向
2.1 ドイツの動向
2.2 国際会議の動向
3.国内の開発動向
3.1 国家プロジェクトの動向
3.2 国内学会の動向
4.マイクロリアクタの市場規模
5.環境負荷低減への取組み動向
5.1 グリーンサスティナブルケミストリー
5.2 E-factor (E-ファクター)
第4章 シミュレーション活用によるプロセス革新の予測技術
1.シミュレーション活用の重要性
2.液相反応プロセスでの収率の予測シミュレーション
2.1 モンテカルロ法
2.2 分子の移動規則
2.3 対象反応場と分子の衝突規則
2.4 アルゴリズム
2.5 シミュレーション結果
2.6 無次元数による整理
3.液相反応プロセスでの反応速度定数の予測シミュレーション
3.1 反応速度式の構築
3.2 ペトリネット法による反応速度定数の予測手法
3.2.1 離散ペトリネット
3.2.2 連続ペトリネット
3.2.3 ハイブリッドペトリネット
3.3 反応速度定数の予測
3.3.1 逐次反応の実験結果
3.3.2 撹拌槽方式バッチ反応の場合
3.3.3 マイクロリアクタの場合
3.3.4 反応速度定数の予測結果
4.液相反応プロセスでの溶媒効果の予測シミュレーション
4.1 拡散律速と反応律速
4.2 分子軌道法による溶媒効果の予測シミュレーション
4.2.1 分子軌道法
4.2.2 溶媒効果の予測
4.2.3 実験との比較による予測結果の検証
5.乳化プロセスでの液滴生成の予測シミュレーション
5.1 VOF法によるシミュレーション
5.2 シミュレーション条件
5.3 無次元数による整理
5.4 実験との比較による予測結果の検証
第5章 マイクロリアクタによるプロセス革新と環境負荷低減の事例
1.実験法と適用プロセスの分類
1.1 マイクロリアクタを用いた実験法
1.2 攪拌槽方式バッチ法を用いた実験法
1.3 適用プロセスの分類
2.液相反応プロセス
2.1 攪拌槽方式バッチ法の課題
2.2 液相反応の分類とマイクロリアクタ適用の効果
2.3 競合反応の事例
2.3.1 ダッシュマン反応
2.4 逐次反応の事例
2.4.1 ブロム化反応
2.4.2 ニトロ化反応
2.4.3 エステルの還元反応
2.4.4 エステルのグリニャール反応
2.4.5 アセチル化反応
2.5 平衡反応の事例
2.5.1 エステル化反応
2.5.2 エステル交換反応
3.ナノ粒子生成プロセス
3.1 ナノ粒子生成法の分類
3.2 攪拌槽方式バッチ法の課題
3.3 ナノ粒子径の均一化
3.4 混合性能の影響
4.乳化プロセス
4.1 乳化の基礎
4.2 攪拌槽方式バッチ法の課題
4.3 乳化液滴径の均一化
5.液液抽出プロセス
5.1 バッチ法の課題
5.2 分析バラツキの低減
5.3 超音波振動利用による乳化分離時間の短縮
6.濃縮プロセス
6.1 バッチ法の課題
6.2 機能性食品への適用
第6章 マイクロリアクタのプラント化
1.ナンバリングアップ
2.実証プラント化の動向
3.実証プラントの事例
3.1 外部ナンバリングアップ方式のプラント
3.2 内部ナンバリングアップ方式のプラント
4.将来展望