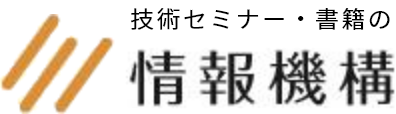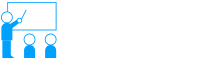![]() ……会場(対面)受講
……会場(対面)受講
★産業分野問わず、熟練技術者からの技術継承でお困りの方必見!
★皆様の現場に沿った技術継承アクションプランをすぐに作成できる実践セミナー!
★本講座はPCを用いた実習形式で行います。注意事項についてはセミナー詳細をご確認ください。
講師
株式会社オレンジテクラボ 代表取締役 兼 事業創造大学院大学 MOTプログラム教授 宮﨑 淳 氏
講師紹介
■経歴
1989年 慶應義塾大学大学院 / 理工学部電気工学専攻 / 後期博士課程修了 / 工学博士
1988年富士ゼロックス(株)入社、主幹研究員を経て、2016年早期退職。2017年~現在(株)オレンジテクラボ設立。2016〜2018年国立研究開発法人産業技術総合研究所客員研究員。現在、事業創造大学院大学 MOTプログラムディレクター、教授。
開志創造大学情報デザイン学部設置準備室ディレクター、学部長就任予定。
■専門および得意な分野・研究
専門分野 : 計算機アーキテクチャ、ソフトウェア、人工知能、技術経営、技術マーケティング
■本テーマ関連学協会での活動
日本MOT学会、日本ソーシャルサイエンス学会、
米国 ACM(American Computing Machinery )各会員
<その他関連セミナー>
新規事業・マーケティング・ビジネススキル 一覧はこちら
日時・会場・受講料・お申込みフォーム
●日時:2025年8月29日(金) 13:00-16:00 *途中、小休憩を挟みます。
●会場:[東京・大井町]きゅりあん 5階第3講習室 →「セミナー会場へのアクセス」
●受講料:
【会場受講】:1名40,700円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,700円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
お申込みはこちらから
会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。
●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。
●録音・撮影行為は固くお断りいたします。
●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。
●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)
セミナーポイント
■講座のポイント
日本では団塊の世代の引退とともに、長年蓄積された貴重な技術やノウハウが現場から失われつつあります。本講座では、技術継承の課題を参加者自身が直視し、自社の現場に即した具体的なアクションプランを作成・共有することを目的とします。
生成AIを活用しながら、SECIモデルを軸に暗黙知の形式知化の理論と実践を結びつけ、各参加者が「明日からできる」行動を持ち帰る、実践的な内容です。
また、現場記録の際の法令順守事項や、熟練技術者の雇用・処遇に関する施策にも触れ、実現可能な技術継承を支援します。
■受講後、習得できること
1. 現場の技術継承課題を「見える化」し、言語化・構造化する視点
→ 暗黙知を形式知にする思考とSECIモデルの活用方法を体得。
2. 生成AIを用いた技術伝承支援の実践的な使い方
→ ChatGPT等を使ってノウハウの抽出・記録・マニュアル化ができる。
3. 自社に即したアクションプランの立案スキル
→ 漠然とした課題から具体的な取り組みへ落とし込む技法を習得。
4. 他者との協働による多角的な気づきと解決策の発想力
→ 異なる業界や職種の視点から学び合い、応用力を広げる。
5. 技術を持つ人材を守り、活かし続けるための制度・方針の視点
→ 定年延長・専門職活用など、人的資源のリテインに関する実践知を得る。
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
講義の中でも明確にしますが、以下の法規・ガイドラインがあります。
・肖像権保護(記録映像の匿名化など)、撮影前に承諾書の取得
・著作権・知的財産権の明示
・技術継承動画・マニュアルの社外利用制限
・データの保管・管理ツールの設定と運用
■講演中のキーワード
#技術伝承、#暗黙知、#形式知、#生成AI、#実践的、#アクションプラン
セミナー内容
<受講にあたり①:PCご持参のお願い>
当日は生成AI(ChatGPT等)を用いた技術伝承のポイントを解説していきます。
実際にお手元でも操作しながらご受講をいただきたく、
【可能であれば有料版ChatGPT、難しい方は無料版のChatGPT等の生成AIを準備したPC】をご持参いただけますと幸いです。
<受講にあたり②:グループワークのご案内>
講義後半、2-3人ずつのグループ分けを行い、
技術継承課題へのアプローチを学んでいただきます。
可能な範囲で構いませんので、皆様の技術継承における課題点をお持ちの上でご参加ください。
【第1部】
1.オープニング
「なぜ今、技術継承が問題なのか?」
2.技術継承の現状と課題
団塊世代の引退、属人化した技術、現場の変化などをデータと事例で紹介。
3.暗黙知と形式知:SECIモデルの基本
SECIモデルの4つのプロセス(共同化・表出化・連結化・内面化)を簡潔に紹介。
4.技術継承の成功・失敗事例紹介
以下の具体例を通じて、課題と成功の要因を共有:
- 危険物運搬大型車両の五感による点検 → AI+動画で形式知化
- 人間国宝による伝統技術 → センサー+VRで再現
- プラントメンテナンス → ARで遠隔熟練指導
- 食品製造の「感覚」 → AI画像分析+コメント
- 中小製造業の旋盤加工 → GoPro+生成AIでプロトコル化
5.生成AI活用による支援事例
ChatGPTや音声認識AIを活用した「形式知化支援」の方法:
対話ログの自動要約、FAQ自動生成、作業マニュアル構築支援など
6. 熟練技術者のリテイン施策
継承を実効性あるものにするために、技術保有者への待遇配慮策:
- 定年延長制度の導入
- 専門職としての再雇用、社内資格制度の創設
- 年齢に見合った妥当な職位・処遇設計
- 高齢者雇用安定法との整合性確認
- ノウハウ伝承に特化した「後進育成職」の創設例
7.記録・可視化の際の法令順守と知的財産管理
生成AI・記録機器の活用にあたり、次のような対応が必要:
- 肖像権保護:記録映像にモザイク処理/承諾書取得
- 著作権・知的財産権:企業が権利を保有する旨の契約明記
- 社外利用制限・公開範囲の明確化
- データ保管・管理ルールの設定
8.演習の説明と期待
「技術の灯を絶やさないために、あなたの現場でできることは?」
【第2部】演習・グループワーク
1. 個人観察ワーク:自社の技術継承課題を洗い出す
2. グループ内共有と意見交換
3. グループ代表による全体発表
4. グループワーク:アクションプランづくり
5. 決意表明プレゼン
お申込みはこちらから