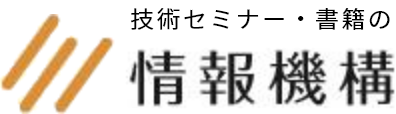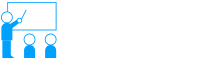![]() ……Zoomオンライン受講
……Zoomオンライン受講
![]() ……見逃し視聴選択可
……見逃し視聴選択可
★微細藻類の大量培養技術、藻類ごとの特徴や今後の応用展開、事業化/新規参入のためのポイントなど、重要トピックスを包括的に解説!
講師
濱崎研究室 代表 濱崎 彰弘 氏
講師紹介
■経歴
1987年3月 大阪大学基礎工学研究科化学工学専攻 前期課程修了(工学修士)
1987年4月 三菱重工株式会社 入社 高砂研究所配属
2003年10月 同 高砂プラント技術部高砂プラント機器設計課
2023年1月 濱崎研究室 開業
2023年9月 三菱重工株式会社 退職
2024年5月 株式会社Blossom Energy 入社(個人事業との兼業)
■専門および得意な分野・研究
技術士(機械部門/動力エネルギー、総合技術監理部門/機械、環境部門/環境保全計画、生物工学部門/環境生物工学、化学部門/化学プロセス、経営工学部門/サービスマネジメント)
地球温暖化対策技術、バイオマスの利活用技術、各種(品質、情報セキュリティ、環境、プロジェクト、コスト、従業員教育他)マネジメント
■本テーマ関連学協会での活動
1.松本曠世.浜崎彰弘,塩地則夫,北吉博,”人工えらを適用した小閉鎖径生命維持システムの基礎研究”,イヒ学工学論文集,第18巻,第5号,pp584-592(1992)
2.松本曠世,浜崎彰弘,”クロレラの酸素発生速度および酸素消費速度の簡便な測定法とその応用”,化学工学論文集,第18巻,第5号,pp763-766(1992)
3.松本曠世,浜崎彰弘,”微細藻類の健全性評価への酸素反応モニターへの適用”, Nippon Suisan Gakkaishi, 第59巻,第2号,pp279-283(1993)
4.松本曠世,浜崎彰弘著,山口勝己偏,”微細藻類の利用 第10章”,恒星社厚生閣
5.M. Negoro, N. Shioji, A.Hamasaki, Y. lkuta, T. Makita, K. Hirayama, S. Suzuki, “Carbon Dioxide Fixation by Microalgal Photosynthesis Using Actual Flue Gas Discharged from a Boiler”, Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol.39/40,pp643-653(1993)
6.A.Hamasaki, N. Shioji, Y. lkuta, Y.Hukuda, T. Makita, K. Hirayama, and S. Suzuki, “Carbon Dioxide Fixation by Microalgal Photosynthesis Using Actual Flue Gas from a Power Plant”, Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol.45/46,pp799-808(1994)
7.H. Matsumoto, N. Shioji . A. Hamasaki, Y. lkuta, Y. Hukuda, M. Sato, N. Endo and T. Tsukamoto.“Carbon Dioxide Fixation by Microalgal Photosynthesis Using Actual Flue Gas from a Power Plant”, Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol.51/52,pp681-692(1995)
8.松本曠世.浜崎彰弘,”微細藻の光合成速度に及ぼす溶存酸素の影響”,化学工学 第58巻, pp382-383(1995)
9.濱崎彰弘,” O-14微細藻の最適培養法の検討”,第12回バイオマス科学会議論文集, pp27-28(2017)
10.濱崎彰弘,” P-36微細藻類の大量培養法の検討”, 第13回バイオマス科学会議論文集, pp117-118(2018)
11.濱崎彰弘,” 2-4 微細藻類の高効率バイオリアクターとそれを利用した火力発電所ガス交換システム”, 第14回バイオマス科学会議論文集, pp19-20(2019)
12.各節共著、バイオプロセスを用いた有用物質生産技術、第4章16節 微細藻類を利用した火力発電所CO2固定バイオ燃料生産技術の開発、㈱技術情報協会(2022)
<その他関連セミナー>
スマート農業・藻類・培養肉・植物工場 一覧はこちら
日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2025年6月27日(金) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
お申込みはこちらから
配布資料・講師への質問など
●配布資料はPDFなどのデータで配布いたします。ダウンロード方法などはメールでご案内いたします。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。
(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
※メールアドレスの記載誤りについては、以下へご連絡お願いいたします。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
→Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、カメラ・マイクが使えないなどの事象が起きる可能性がございます。お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
→音声が聞こえない場合の対処例
→一部のブラウザは音声が聞こえないなどの不具合が起きる可能性があります。
対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
(iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)
→見逃し視聴について、 こちらから問題なく視聴できるかご確認ください。(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」
<見逃し視聴ご案内の流れ・配信期間詳細>
セミナーポイント
■講座のポイント
微細藻類は生産速度が大きく、海水でも生育可能なので農地と競合せず、連作障害がなく、アルコール、油分、水素など燃料を生産する種があり、食料や健康食品としての利用も可能である。そのためこれまで、食料や餌料、健康食品やバイオ燃料など種々の微細藻類の利活用の検討が行われてきた。
本講演では、微細藻類の利活用について基礎的なところから応用まで、幅広い内容構成になっている。特に、これまで世界で100年近い取り組みが行われているにも関わらず、大量培養に成功しているのがクロレラ、スピルリナ、ドナリエラ、ユーグレナなど10種に満たないところにフォーカスして、屋外開放型レースウェイ培養槽の大量培養技術及び実用化のポイント、課題などについて取り上げるとともに、取り組み事例が少ない人工光源のバイオリアクターによる構造が簡単で、建設費が低廉で据付面積が小さい濡壁塔型バイオリアクターと、それを利用した再生可能エネルギーカーボンリサイクルシステムについて述べる。
■受講後、習得できること
・微細藻類の事業化のポイント
・微細藻類の大量培養法のポイント
・微細藻類のバイオリアクターの設計法
・微細藻類の実験施設の計画
・微細藻類の性能評価法
■受講対象
・微細藻類の事業化を計画している方
・微細藻の培養をしている方
・微細藻の大量培養を検討している方
・微細藻の高効率培養できるリアクターの設計法を学びたい方
・微細藻の培養で問題点の解決法や課題の達成方法を知りたい方
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・ASTM D7566 Annex7 微細藻類を原料とする持続可能な航空燃料(SAF)規格
■講演中のキーワード
微細藻類、大量培養、バイオリアクター、バイオ燃料、生理活性物質、食料増産
セミナー内容
1.微細藻類の特長
1-1.バイオマスとして
1-2.エネルギー生産や炭素固定バイオマス
1-3.他の植物と微細藻類の比較
1-4.微細藻類の研究開発の歴史
2.微細藻類の用途
2-1.エネルギー
2-2.健康食品、生化学物質
2-3.飼料、餌料
2-4.廃水処理
2-5.宇宙空間
3.事業化済、あるいは事業化が期待されている有用藻類
3-1.クロレラ
3-2.スピルリナ
3-3.ドナリエラ
3-4.ユーグレナ
3-5.ボツリオコッカス
4.微細藻培養、取扱技術(ラボスケール)
4-1.微細藻類の入手法
4-2.微細藻類の培養設備
4-3.微細藻類の培養
4-4.微細藻類の光合成能力測定
4-5.微細藻類のスクリーニング
5.大量培養技術と課題
5-1.屋外開放型培養槽(レースウェイ型)
5-2.密閉型バイオリアクター
・屋外密閉型培養槽(チューブ型、プレート型)
・側面出光型光ファイバー型培養槽
・LED照射濡壁塔塔型培養槽
5-3.培養槽の設計
6.事業化/新規参入のポイント
6-1.有価物の価格、ニーズ、市場
6-2.生産コスト(設備投資、運転コスト)
6-3.環境価値
・カーボンニュートラル
・持続可能性
・物質循環システムを構成
<終了後、質疑応答>
お申込みはこちらから