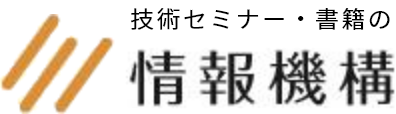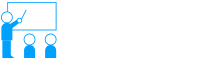![]() ……会場(対面)受講
……会場(対面)受講
★各業界の品質トラブル事例を参考にして,発生原因を探り出し,どうしたら再発防止・未然防止ができるかを学ぶ
★明日からできる身近な改善策とは?
講師
(株)ウテナ 技術顧問 深澤 宏 氏
講師紹介
■経歴
昭和52年コーセー入社
平成4年アルビオン転籍
平成30年ウテナ再就職(現在技術顧問として社内教育に従事している)
現在に至る
■専門および得意な分野・研究
品質管理,品質工学(タグチメソッド),化粧品技術(生産技術,品質保証,品質管理),経営工学(生産改善,失敗学,リスクマネジメント)
■本テーマ関連学協会での活動
粧工会常任理事会委員,品質工学会代議員,日本品質管理学会会員,日本技術士会会員,品質工学フォーラム埼玉顧問,
<その他関連セミナー>
化粧品・医薬部外品・食品 一覧はこちら
日時・会場・受講料・お申込みフォーム
●日時:2025年10月23日(木) 10:30-16:30 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。
●会場:[東京・大井町]きゅりあん 5階第1講習室 →「セミナー会場へのアクセス」
●受講料:
【会場受講】:1名50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
お申込みはこちらから
会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。
●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。
●録音・撮影行為は固くお断りいたします。
●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。
●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)
セミナーポイント
■講座のポイント
化粧品の製造販売制度は,平成17年(2005年)に薬事法改正により,企業の市場に対する責任の明確化,市販後安全対策の充実・強化,国際整合性の確保等を目的に,製造販売業許可と製造業許可が分離されました.
製造販売業者には総括製造販売責任者の設置が義務付けられ,品質管理の基準(GQP)と製造販売後安全管理の基準(GVP)が導入されました.
一方,化粧品GMPは,昭和56年(’81年)1月に日本化粧品工業連合会の自主基準として「化粧品の製造及び品質管理に関する技術指針(化粧品等GMP)」が設定されました.
その後,欧州統合を受けてISO化による標準化が進められ, TC217において,平成14年(’02年)から「化粧品GMP」の検討がなされ,平成19年('07年)11月15日付けにて,化粧品GMPが「国際規格(IS)」として公表されました。
現在,ISO22716(化粧品GMP)の和訳版が業界推奨の規格となりました。
しかし,GMP制度が許可要件となっている「医薬品業界」において,様々は品質トラブルが散見されています。これを受けて厚労省は「法令順守体制の構築」を軸とする薬機法改正が行われました。
化粧品業界においても,品質トラブルによる「自主回収」は後を絶たず,GMPの実効性が危ぶまれます。
本稿では,各業界の品質トラブル事例を参考にして,発生原因を探り出し,どうしたら再発防止・未然防止ができるかを学びます。
最終目標は“Quality Culture”の醸成ですが,到達するまでの具体的な手法や手順,規範などから,明日から実践できる身近な改善策を議論します。
日本の化粧品がこれからも「Japan Quality」を世界に発信し続けることを願っています。
■受講後、習得できること
ISO22716(化粧品GMP)の目的と運用手順
ICH Qトリオの考え方と運用方法
失敗学の考え方と取り組み手順
継続改善の基本であるQCストーリーの手順
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
ISO22716 ICH Qトリオ
■講演中のキーワード
GMP,Quality by Design,Quality Culture,リスクマネジメント,品質システム,継続改善,QCストーリー,CAPA,OOS,逸脱,バリデーション,再発防止,未然防止
セミナー内容
導入部:化粧品GMP概論
0.薬機法と化粧品GMPの関係
1.GMPの基礎
2.化粧品GMPの変遷
3.ISO-22716(化粧品GMP)の概要
4.ISO-22716(化粧品GMP)の認証制度
5.GMPの運営方法
第1部:日本の製造業と化粧品産業の実態
1.日本の製造業の衰退
2.化粧品規制の変遷
3.化粧品製造業者
4.化粧品GMPとGQPの関係(守備範囲)
5.製・販分離の弊害
第2部:どうして減らないのか「自主回収事例」
1.医薬品業界での違反事例
2.化粧品業界の実態
3.微生物汚染・異物混入の対応
4.品質不良の対応
5.法令違反への対応
6.誤使用の対策
7.薬事表示の誤記対応
まとめ
第3部:PMDA指摘事項の解析
目的
事例集(GMP指摘事例速報(オレンジレター)一覧)より
1.原料の受入時に供給元の確認を適切に行わなかった事例
2.医薬品を製造する作業室で、薬理作用・毒性が不明な治験薬を製造していた事例
3.OOS処理において他のロットへの影響評価が不十分であった事例
4.試験業務の委託に際し、外部試験検査機関の適正・能力の確認が不十分であった事例
5.憶測に基づいて記録を作成した事例
6.指図書との整合を図るために記録を修正した事例
7.製品に内容物と異なるラベルが貼付された事例
8.汚染リスクを過小評価している恐れのある事例
9.品質異常の兆候を見逃し、措置を講じていなかった事例
10.製造現場の実態を正確に報告できていなかった事例
11.経営陣が製造現場の改善状況を把握していなかった事例
12.バリデーション時に必要なリスク評価が不足していた事例
13.出荷不適品を不適切に取り扱っていた事例
14.担当部門のみで、変更管理を不要と判断した事例
15.後発医薬品関連製造所で最近認められた不備事例
16.承認事項等の不遵守及び虚偽の記録作成に関する事例
17.リスクに応じたバリデーション計画の立案について(その2)
18.多品目を製造する製造所で認められた不備事例
19.安定性モニタリングに関する試験結果の取扱いについて(その2)
20.承認事項との相違の背景にある問題が示唆された事例
第4部:Quality Cultureの重要性と失敗学の活用
1.化粧品の品質保証とは
2.相次ぐ医薬品業界の不祥事
3.何故今Quality Cultureなのか
4.品質リスクマネジメントを活用した「未然防止」
5.失敗学を用いた未然防止
6.事例で学ぶ失敗学
7.継続改善の勧め
Q&A
お申込みはこちらから