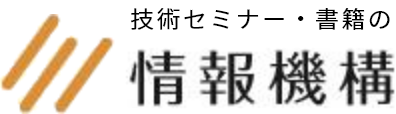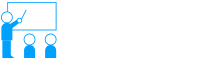![]() ……会場(対面)受講
……会場(対面)受講
〇閉鎖循環式養殖システムを構成する各装置の必要性と選定のポイントとは?
〇陸上養殖に興味のある方や関わっている方は、是非ともご参加ください。
〇閉鎖循環式養殖の研究事例、コストの検討方法、コスト低減のポイントについてもお話させていただきます。
講師
技術士事務所アクアテラス 代表 吉野 博之 氏
講師紹介
■略歴:
大学卒業後、自動車会社を経て1987年テクノポリス函館技術振興協会(北海道立工業技術センター)入所、水産等の省力化機器開発に従事。1995年に陸上養殖システムの研究に着手、1996年に欧米の陸上養殖施設を視察後、閉鎖循環式養殖システムに関する研究開発を開始。脱窒装置を備えた閉鎖循環式養殖システムにより、ペヘレイを1年間飼育することに成功。その後、閉鎖循環式陸上養殖の経済性やアワビとガゴメコンブとの閉鎖循環複合養殖(アクアポニックス)等について研究。2024年4月から現職。2003年北海道大学大学院水産科学研究院博士後期課程修了、「閉鎖循環式養殖システムに関する研究」により博士(水産科学)取得、技術士(水産部門)
■専門および得意な分野・研究:
閉鎖循環式養殖システム、活イカ輸送、釣りオモリに関する研究等
<その他関連セミナー>
陸上養殖・養殖技術 一覧はこちら
日時・会場・受講料・お申込みフォーム
●日時:2026年2月18日(水) 13:00-17:00 *途中、小休憩を挟みます。
●会場:[東京・浮間舟渡]板橋区立企業活性化センター2階第1研修室 →「セミナー会場へのアクセス」
●受講料:
【会場受講】:1名46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
お申込みはこちらから
会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。
●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。
●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。
●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)
●講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。また、申込者以外の受講・動画視聴は固くお断りいたします(代理受講ご希望の際は、開催前日までに弊社までご連絡お願いします)。
セミナーポイント
■はじめに
近年、気候変動、環境問題、食料自給率向上、SDGs、地域振興等の観点から閉鎖循環式陸上養殖が注目を集めており、実際に各地域において大小様々な規模で閉鎖循環式陸上養殖が試みられている。しかし、閉鎖循環式陸上養殖の最大の問題点はコスト問題とされ、その成否も最終的には飼育生産コストで決まり大きな課題となっている。これらの養殖システムは様々な装置で構成され、飼育魚種や飼育密度によって各装置の必要要件は異なり採算性にも大きく影響する。そのため、その機能や必要性を理解した上でシステムを構築することが極めて重要である。
本セミナーでは、閉鎖循環式養殖システムを構成する各装置の必要性と選定のポイントからシステム構築の考え方、閉鎖循環式養殖の研究事例、閉鎖循環式養殖のコスト構造、コスト低減のポイントについて詳細に解説する。
■ご講演中のキーワード:
陸上養殖、閉鎖循環式、養殖システム、養殖コスト
■受講対象者:
閉鎖循環式養殖システムの基本を学びたい方、これから陸上養殖に参入したい方から、すでに参入・研究開発を開始しているが改善を図りたい方まで
■必要な予備知識や事前に目を通しておくと理解が深まる文献、サイトなど:
・この分野に興味のある方なら、特に予備知識は必要ない。
■本セミナーで習得できること:
・閉鎖循環式陸上養殖の基礎知識
・システム構成装置の必要性
・システム構築の進め方
・閉鎖循環式養殖のコスト構造
・効果的なコストダウン方法
★過去、本セミナーを受講された方の声【一部抜粋】
・陸上養殖事業立ち上げのための知識習得のために参加させて頂きました。
陸上養殖の可能性及び将来性についても知ることができて良かったです。
・新規事業として、陸上養殖事業化検討のために参加させていただきました。
コスト管理のお話は非常に興味深いお話でした。
・陸上養殖の現状と課題について知りたくて参加しました。講義中の質問にも丁寧に
回答いただきありがとうございました。
・陸上養殖における課題が具体的に書かれていたので、これから取り組んでいく人に向けて
分かりやすい内容でした。
・ほぼ知識が無い状態で受講したのですが、とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
・陸上養殖に取り組む上での注意点やポイントについて知りたくて参加させていただきました。
的確なアドバイスを頂けたので参加して良かったです。
・陸上養殖について学びたく参加させて頂きました。事前質問にも丁寧にご対応頂けたので参加して良かったです。
などなど……ご好評の声を多数頂いております!
セミナー内容
1.陸上養殖の概要
1)養殖システムの分類と特徴
・かけ流し式と循環式のメリット・デメリット
2)魚が水中でやっていること
・魚の代謝
・魚の摂餌から排泄まで
・アンモニアの毒性と耐性
2.閉鎖循環式養殖システムの構築
1)システムの基本構成と流れ
2)閉鎖循環式養殖システムの要素技術とは
3)飼育ユニット
・水槽
・水槽の自己洗浄機能
・給水口と排水口(排水システム)
4)物理濾過
・沈殿槽(沈降分離)
・機械式濾過 スクリーンフィルター
・深層濾過(ディプス濾過) 砂濾過
・泡沫分離
5)生物濾過とは
・硝化
・硝化とアルカリ度とpH
・脱窒
6)生物濾過槽(硝化槽)の種類
・生物濾過槽の濾材
・種類(散水濾床、浸漬濾床、流動床)
・生物濾過槽(硝化槽)管理上の注意点
・硝化槽の立ち上げ
7)pH
8)アルカリ度
9)溶存酸素
10)溶存二酸化炭素
11)飼育水の殺菌
12)循環ポンプ
13)水温制御
14)危機管理
15)その他
16)各装置の不具合要因と不具合発生時の魚への影響
17) 閉鎖循環式養殖のリスク
3.主要装置の検討方法
1)生物濾過の硝化能力
・硝化能力の計算方法
・硝化反応に関する温度の影響
・硝化速度とアンモニア濃度との関係
・硝化速度と流量との関係
・生物濾過槽(硝化槽)の容量計算方法
・必要データと手順、窒素負荷量、硝化速度、濾過槽容量の計算
2)脱窒
・硝酸の低減について
・脱窒は必要か
・脱窒の実際
・脱窒による水質変化
・脱窒装置設計例
3)酸素消費と供給方法
・なぜ酸素が必要か(必要性)
・目標と許容範囲(DOの設計値)
・必要酸素量の求め方
・魚の酸素消費と硝化による酸素消費
・酸素供給方法
4)溶存二酸化炭素とその除去
・溶存二酸化炭素の発生源と蓄積
・高濃度CO₂の影響
・CO₂除去の主な方法
5)循環ポンプ
・必要流量の考え方、揚程とシステム抵抗
4.閉鎖循環式養殖システムの実験事例
1)実験システム概要(物理濾過装置、生物濾過装置)
2)システムの立ち上げと日常業務
3)1年間水換えせずに飼育、その全経過について
・ぺぺレイの飼育事例
4)窒素収支と浄化機構
5)閉鎖循環式養殖における排水
6)流速の影響
7)発生した不具合と対策
8)その他の研究(ガゴメコンブ、アワビ)
5.閉鎖循環式養殖のコスト
1)システム運用コストとシミュレーション
・試算の基本条件
・試算方法
2)閉鎖循環式養殖のコスト構造とその内訳
・設備
・生産原価
・償却費
・運転経費
・電力など
3)閉鎖循環式養殖のコストに及ぼす影響
・設備の影響
・生物的影響
4)効果的なコストダウン方法とは
5)飼育密度とコストの関係
6)水槽容量・運用方法とコストの関係
7)廃熱利用、自然エネルギーの利用の効果
お申込みはこちらから
セミナーコード:AC2602C7