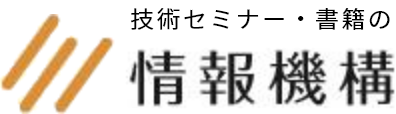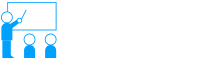![]() ……Zoomオンライン受講
……Zoomオンライン受講
![]() ……見逃し視聴選択可
……見逃し視聴選択可
○AIを使えば誰でも「明細書っぽいもの」が作れる時代に必要な “経営に効く” 特許出願の考え方とは?
○準備や前提理解から、AIを活用した出願までの実務フロー例や特許明細書の作り込み、人が行う「判断と設計」のポイントまで。
講師
きのか特許事務所 代表弁理士 室伏 千恵子 氏
講師紹介
弁理士
AIPE認定知的財産アナリスト(特許)
慶應義塾大学理工学部(物理情報工学科) 卒業
慶應義塾大学院理工学研究科(総合デザイン工学)修士課程修了
AGC株式会社中央研究所にて研究開発に従事。その後、都内および横浜の特許事務所の勤務を経て、2022年に、現・きのか特許事務所を設立。
<その他関連セミナー>
特許・知財/契約/ライセンス・法務 一覧はこちら
日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2026年2月5日(木) 13:00-16:00 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 40,700円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,700円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
お申込みはこちらから
配布資料・講師への質問など
●配布資料はPDFなどのデータで配布いたします。ダウンロード方法などはメールでご案内いたします。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。
(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
※メールアドレスの記載誤りについては、以下へご連絡お願いいたします。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
→Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、カメラ・マイクが使えないなどの事象が起きる可能性がございます。お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
→音声が聞こえない場合の対処例
→一部のブラウザは音声が聞こえないなどの不具合が起きる可能性があります。
対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
(iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)
→見逃し視聴について、 こちらから問題なく視聴できるかご確認ください。(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」
<見逃し視聴ご案内の流れ・配信期間詳細>
セミナーポイント
■はじめに:
AIを活用すれば、誰でも「明細書っぽいもの」を作成できる時代になりました。しかし、AIが書いた特許明細書は審査で「通す」ことはできるかもしれませんが、「経営に効く」特許になるとは限りません。
本セミナーでは、知財部を持たない中小企業やスタートアップが、自社のビジネスに沿った“使える特許”を権利化するための考え方と実務を紹介します。AIを業務に取り入れながらも、人が判断し、経営に活かす知財設計をどのように行うかのポイントを解説します。
■受講対象者:
・知財部を持たない中小企業・スタートアップの経営者、役員、技術責任者
・新規事業・技術開発において知財活用を検討している方
・生成AIを業務に取り入れたいが、実際の使い方を知りたい方
・「AIで明細書が作れるなら、自社でも出願できるのでは?」と感じている方
■必要な予備知識:
特にありません。知財業務や特許出願の経験がなくても理解できる内容です。
経営、開発、知財いずれの立場の方でも受講可能です。
■本セミナーで習得できること:
・AIを活用した特許業務の動向
・経営に貢献する「経営に効く特許」の考え方
・ビジネスモデル理解から出願までの実務フロー
・出願目的に応じた特許明細書の作り込みのポイント
・AIを活かしつつ、人が行う“判断と設計”のポイント
・ “経営に使える” 特許を作り込むための社内対話・発明抽出の工夫
など
セミナー内容
1.AI時代の特許実務の現状と課題
(ア) 「AIで明細書が書ける」時代とは何か
(イ) AIが得意な工程/不得意な工程
(ウ) ChatGPT等の活用実例:特許調査・中間処理支援・ドラフト作成
(エ) AI出力をそのまま使うリスクと品質評価の必要性
2.AIを活かすための前提:出願の“目的”を明確にする
(ア) なんのために出願するのか?
(イ) 出願目的3類型の整理
(ウ) 出願目的とAI活用の関係性
3.ビジネスモデル理解から始まる特許づくり
(ア) 発明より先にビジネスを理解する
(イ) ビジネスモデル図解の活用方法
(ウ) 経営方針・事業ロードマップとの整合確認
(エ) 発明抽出ミーティングの進め方
4.実務フロー例とAI活用ポイント
(ア) 実務フロー例
1) ビジネスモデル理解
2) 事業方針を確認
3) 出願目的を決定
4) 発明理解
5) 出願内容を決定
6) AI補助型明細書作成
(イ) AIを“一工程ごと”に分けて使う考え方(1モデル1工程の原則)
(ウ) AI出力を評価するチェック視点
(エ) 明細書ドラフトをどう“経営に活かす資料”に変えるか
5.「通すための特許」ではなく「経営に効く特許」を作る
(ア) 「審査官に伝わる文章」と「技術者に伝わる文章」
(イ) 通すことだけを目的にしない:経営との接続
(ウ) 特許は他社の事業の進行を鈍らせる戦略ツール
6.AIを使いこなすための考え方
(ア) AIの出力を評価できなければ、的確に使えない
(イ) AIを使う前に:アウトプットをイメージする
(ウ) AIは判断を代替するものではなく、“判断に時間を再配分する”ためのツール ~人がより深く考えるために使うもの~
7.まとめと質疑応答
お申込みはこちらから
セミナーコード:AD260226