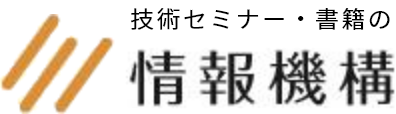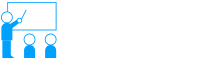![]() ……Zoomオンライン受講
……Zoomオンライン受講
●従来の難燃化技術の復習と新たな難燃化技術の開発方法、難燃性高分子材料を用いる製品設計の考え方を新旧のパラダイムにより対比して解説する。
講師
株式会社ケンシュー 代表取締役社長 倉地 育夫 氏
講師紹介
1.経歴
(1)学歴
1977年 3月 国立名古屋大学工学部合成化学科卒業
1979年 3月 同 大学院工学研究科応用化学専攻博士課程前期修了
1983年 4月 科学技術庁無機材質研究所留学(1984年10月まで)
1992年 9月 学位取得(工学博士:私立中部大学)
(2)職歴
1979年 4月 ブリヂストンタイヤ株式会社入社(現:株式会社ブリヂストン)
1984年11月 株式会社ブリヂストン研究開発本部復職
1991年 9月 株式会社ブリヂストン退社
1991年10月 コニカ株式会社第四開発センター入社(主任研究員)
1993年 4月 国立福井大学工学部客員教授
1993年11月 コニカ株式会社感材技術研究所主幹研究員
1998年 6月 同社MG開発センター主幹研究員
2001年 8月 同社中央研究所所長付主幹研究員
2005年 8月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社生産本部
生産技術センターデバイス技術部第3デバイスグループリーダー
2008年10月 同社生産技術センターデバイス技術部担当部長
2009年 4月 同社開発本部化製品開発センター機能部材開発部担当部長
2011年 3月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 定年退社(57歳)
2011年 3月 株式会社ケンシュー設立 代表取締役社長就任 (現在に至る)
2.受賞歴
2000年 5月 第32回日本化学工業協会技術特別賞受賞
2004年 5月 写真学会ゼラチン賞受賞
(その他 (株)ブリヂストンの超高純度βSiC半導体技術が日本化学会化学技術賞受賞)
3.過去の学会関係の役職
高分子学会代議員、高分子同友会開発部会世話人、日本化学会代議員、日本化学会産学交流委員会シンポジウム分科会主査、同委員長、日本化学会春季年会講演賞審査委員長などを歴任
■専門および得意な分野・研究:
高分子からセラミックスまですべての材料技術
<その他関連セミナー>
プラスチック・高分子・成形加工 一覧はこちら
日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2026年2月18日(水) 10:30-16:30 *途中、お昼休みや小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講】:1名50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
お申込みはこちらから
配布資料・講師への質問等について
●配布資料は、印刷物を1部郵送/PDF等のデータ配布いずれかで調整中です。
・お申込の際は、ご郵送資料のお受け取り可能な住所を必ずご記入ください。
・お申込みは4営業日前までを推奨します。(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・それ以降でもお申込みはお受けしておりますが(開催1営業日前の12:00まで)、配布資料が郵送となった場合、資料到着がセミナー後になる可能性がございます。
・未達の場合などを除き、資料の再配布はご対応できかねますのでご了承ください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
※メールアドレスの記載誤りについては、以下へご連絡お願いいたします。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
→Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、カメラ・マイクが使えないなどの事象が起きる可能性がございます。お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
→音声が聞こえない場合の対処例
→一部のブラウザは音声が聞こえないなどの不具合が起きる可能性があります。
対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
(iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)
セミナーポイント
日本では1993年に環境基本法が制定され、2000年に循環型社会形成推進基本法が制定されて、高分子産業に環境規制が大きな影響を与えるようになった。これは世界が地域環境から地球環境の問題を考える潮流に変化したからである。高分子学会高分子同友会環境分科会では2002年に「環境関連法規制が高分子産業に与える影響とその対応策検討」というまとめを発表している。この時、ハロゲンフリー高分子難燃化技術の開発が重要テーマとして提案されたが、すべての高分子についてハロゲンフリーで高度の難燃化に、未だ対応できていない。一方、高分子のリサイクルを進める世界の潮流もあり、この観点でもハロゲンフリーが求められている。その結果、「レガシー臭素系難燃剤の段階的縮小→代替物質への監視強化→ハロゲンフリーへの代替促進/製品・供給連鎖での開示義務強化」が、難燃剤の世界的規制動向となっている。
この動向を踏まえ、従来の難燃化技術の復習と新たな難燃化技術の開発方法、難燃性高分子材料を用いる製品設計の考え方を新旧のパラダイムにより対比して解説する。高分子の難燃化技術は、エジプトのミイラにもその痕跡があり、温故知新が技術開発に重要な姿勢となる。難燃剤の分散については、科学的に数値化できない場合があり、トランスサイエンスとなる分野であり、製品設計において悩ましい問題に遭遇する場合も出てくる。データサイエンスを手軽に活用できるのはDXのおかげであるが、Pythonのスキルが求められるので、その入り口も解説する。
すなわち、本セミナーは、難燃剤の規制動向を踏まえ、新規技術を開発したい人から従来技術で問題を抱えている人など、担当業務に高分子の難燃化というキーワードが含まれている人すべてに役立つ最新技術情報を解説する。
また、担当業務にそのキーワードが含まれていなくても、高分子材料技術にDXを導入したい人にも参考となるオブジェクト指向的思考法の事例として学習できる構成である。
セミナー内容
1. 高分子の難燃化技術概説
1.1. 火災と高分子の難燃化技術
1. 難燃化メカニズム
2. 炭化促進型難燃化技術
3. 溶融型難燃化技術
1.2. 高分子の難燃化技術研究の歴史
1.3. 難燃性の評価試験法
1.極限酸素指数法
2.UL94評価試験法
3.コーンカロリーメーター
4.その他の評価試験法
1.4. 高分子の難燃化技術とデータサイエンス
2. 難燃剤の規制動向
2.1. 高分子と環境問題
2.2. 国際的な潮流
1.国際条約における規制
2.EU(REACH / POPs / SCIP / RoHS 等)
3.米国(EPA/TSCA)
4.アジア
2.3.日本国内の現状と動向
1.化学物質審査規制法(化審法)
2.業界対応、その他
2.4.注目すべき最近の動きと対応
3.高分子のプロセシングと難燃化技術
3.1.高分子のプロセシング概論
3.2.カオス混合の効果
4.難燃化技術とデータサイエンス
4.1.データサイエンス概論
4.2.Pythonと難燃化技術
4.3.日本化学会発表事例
4.4.オブジェクト指向と難燃化技術
4.5.データ駆動による開発事例
4.6.ホスファゼンのコロイド化
5.まとめ
お申込みはこちらから
セミナーコード:AG2602C8