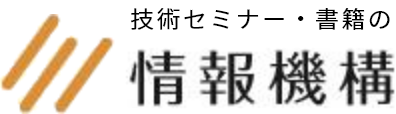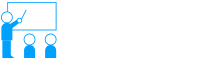![]() ……Zoomオンライン受講
……Zoomオンライン受講
★このようなお悩みはありませんか?
・copilotを導入したが、データ分析や資料作成が思うように進まない…。
・何度も指示を修正しないと、意図した回答が返ってこない…。
・生成されたコードや文章の間違いがどこにあるのか分からず、修正に時間がかかる…。
・「プロンプトの工夫次第」とは言うものの、具体的にどう改善すれば良いか分からない…。
本セミナーは、このような課題を抱える知財ご担当者様のために、生成AIを最大限に活用し、知財業務の質と速度を飛躍的に向上させるための具体的なノウハウを提供する実践的な講座です。
★本セミナーで得られること
・AIから「意図した通りの回答」を引き出すための、具体的なプロンプト設計スキル
・プログラミングを使わずに、明日からすぐに試せる生成AIの業務活用術
・Python等を活用し、データ分析や定型業務を自動化するための第一歩
・AIを業務フローに組み込み、効率化を実現するための具体的な考え方
講師
(株)エンライトオン代表取締役 兼 (株)Zuva AI・MLエンジニア 兼 ミノル国際特許事務所 サーチャー 西尾 啓 氏
講師紹介
■主経歴等
特許事務所およびWeb系企業での実務経験を経て、2018年より早稲田大学にて招聘研究員(知財マネジメント)。専門は、特許調査・分析および知財コンサルティング。ソフトウェア領域を中心に、GoogleCloudを活用したクラウドエンジニアリング、機械学習・ビッグデータ基盤に関する技術的知見を有する。特許情報を対象としたテキスト分析、ポートフォリオ分析、特許分析システムの開発支援などを手がける。著書に「Python(pandas)を用いた特許データの処理」(『情報の科学と技術』2020年4月号)、がある。
■専門および得意な分野・研究
特許調査・分析、自然言語処理
<その他関連セミナー>
特許・知財/契約/ライセンス・法務 一覧はこちら
日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2026年2月10日(火) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講】:1名45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
お申込みはこちらから
配布資料・講師への質問など
●配布資料はPDFなどのデータで配布いたします。ダウンロード方法などはメールでご案内いたします。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。
(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
※メールアドレスの記載誤りについては、以下へご連絡お願いいたします。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
→Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、カメラ・マイクが使えないなどの事象が起きる可能性がございます。お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
→音声が聞こえない場合の対処例
→一部のブラウザは音声が聞こえないなどの不具合が起きる可能性があります。
対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
(iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)
セミナーポイント
■講座のポイント
この講座は、知財業務における生成AIの実践的活用を段階的に学ぶ構成です。第1章では生成AIの基本と知財業務への応用(ChatGPT、Claude、Geminiの使い分け)、第2章ではプロンプト・コンテキストエンジニアリングの技術(Chain of Thought、ReAct等)、第3章ではノーコード自動化(Dify、n8n、FlowiseAI等の活用)、第4章ではAIを業務パートナー化するワークフロー(自作開発vsクラウドサービス、RAG・AI Agent実装)、第5章では完全自動化への道筋(コーディングアシスタント、MCP/A2Aプロトコル)を扱います。プログラミング不要から始まり、最終的には高度なAIエージェントシステム構築まで、知財業務の効率化と自動化を実現する包括的な学習プログラムです。
■受講後、習得できること
・効果的なプロンプト設計の基本構造と原則
・知財業務に特化したプロンプトテンプレート
・コンテキストエンジニアリングの重要性と実践方法
・生成 AI によるコード生成とノーコード開発の 2 つのアプローチ
・自作開発 vs クラウドサービスの選択指針と RAG・AI エージェント実装
・LangChain/LangGraph、Google Agent Development Kit、MCP/ACP の活用
セミナー内容
■講演プログラム
第1章 生成 AI の基本と知財業務への応用
1.1 生成 AI とは?基本の理解
1.2 特別な準備不要!今日から始められる活用方法
1.3 具体的な活用事例:調査・分析業務
1.4 具体的な活用事例:出願・権利化業務
1.5 具体的な活用事例:権利活用・管理業務
1.6 外国語文献の翻訳・理解促進
1.7 技術動向分析レポートの作成支援
1.8 活用の注意点とベストプラクティス
第2章 AI との対話を極める「プロンプト」と「コンテキスト」
2.1 なぜ AI は思ったような答えを返してくれないのか?
2.2 プロンプトエンジニアリングの基礎
2.3 事例で学ぶ!プロンプトのブラッシュアップ体験 - 事例 1: 特許文献の要約
2.4 事例 2: 先行技術調査のキーワード抽出
2.5 事例 3: 明細書作成支援
2.6 プロンプト改善の実践テクニック
2.7 従来のプロンプト手法の限界とコグニティブ・デザイン
2.8 プロンプトの品質評価と改善
2.9 プロンプトライブラリ
2.10 プロンプト形式の選択:マークアップ vs マークダウン
2.11 「プロンプトを生成させる」プロンプト
2.12 コンテキストエンジニアリングの重要性
2.13 コンテキストエンジニアリングとは
2.14 コンテキストエンジニアリングの基本概念
2.15 知財業務でのコンテキストエンジニアリング実践
2.16 一般的なコンテキストエンジニアリングの方法
2.17 コンテキストエンジニアリングの効果測定
2.18 コンテキスト設計例
2.19 コンテキストエンジニアリングのベストプラクティス
2.20 コンテキストエンジニアリング周辺の知識
2.21 プロンプトオーケストレーションマークアップ言語(POML)
2.22 AI エージェントの設計と実装における基盤技術要素
2.23 コンテキストエンジニアリングの役割と戦略
2.24 Anthropic のコンテキストエンジニアリング戦略
2.25 Deep Agents の深堀りで理解する AI エージェント
第3章 知財業務の自動化 - ノーコードからの第一歩
3.1 ノーコード開発の 2 つのアプローチ
3.2 知財業務での自動化事例 - 事例 1: 特許文献の一括処理
3.3 事例 2: 特許検索の自動化
3.4 事例 3: 明細書作成支援システム
3.5 コードが読めない人でもできるコツ
3.6 生成 AI を活用したノーコードツール
3.7 Dify を使った知財業務の自動化
3.8 n8n を使ったワークフロー自動化
3.9 FlowiseAI を使った RAG システム構築
第4章 AI を「業務パートナー」にするための実践的ワークフロー
4.1 AI を単なる「便利な検索ツール」で終わらせないために
4.2 AI を「業務パートナー」としてチームに迎え入れる
4.3 知財業務の質と生産性を向上させる新しい業務フロー
4.4 自作開発 vs クラウドサービス:RAG・AI Agent の実装アプローチ比較
4.5 クラウドベンダー別 RAG アーキテクチャの比較
4.6 導入戦略 段階的導入アプローチ
4.7 効果測定と継続的改善 **効果測定のフレームワーク**
4.8 将来展望と戦略 **技術トレンドへの対応**
4.9 LangChain/LangGraph の利用 LangChain の基本概念
4.10 Google Agent Development Kit の利用
4.11 MCP/ACP の利用
4.12 AI Agent デザインパターンの詳細解説
第5章 知財業務の自動化への道筋
5.1 コーディングアシスタントの活用
5.2 Gemini CLI について
5.3 Claude Code CLI の活用
5.4 寝てる間に進めてもらう(サンプル)
5.5 自動化システムの構築
5.6 自動化の効果測定
5.7 AI エージェントのクラウドベンダー比較
5.8 Vellum AI LLM リーダーボードの活用
5.9 MCP (Model Context Protocol) と A2A (Agent-to-Agent) プロトコル
第6章 その他の資料
6.1 全体まとめ
6.2 クイズ
6.3 参考文献
(質疑応答)
お申込みはこちらから
セミナーコード:AG2602P7