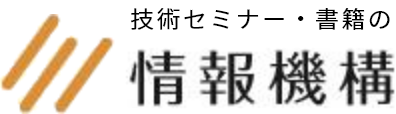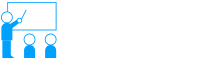![]() ……Zoomオンライン受講
……Zoomオンライン受講
![]() ……見逃し視聴選択可
……見逃し視聴選択可
講師
HBJコンサルティング 代表 髙橋 進 氏
■経歴
1976年~2013年 東芝メディカルシステムズ株式会社(現、キャノンメディカルシステムズ株式会社)
海外営業部門(株式会社東芝医用機器国際部にて中南米グループ長ほか)、マーケティング部門、経営企画部門に従事し、以下の工業会・経済団体等の業界活動に従事。
2015年 HBJコンサルティング創業
2015年 医機連推薦により三菱総合研究所の伴走コンサルタント委員就任(~2020年)。
2015年 医機連推薦により福岡県開発支援コンシェルジュ受託。
2016年 大阪大学よりJST STARTプロジェクトマネージャー受託(~2019年3月)。
2019年 大阪大学発ベンチャー 株式会社APSAM Imagingの創業に参画。
〇日本画像医療システム工業会(JIRA)
前国際委員会委員長/グローバル工業会DITTA(Global Diagnostic Imaging, Healthcare IT & Radiation Therapy Trade Association)の初代ステアリングメンバー。
前医療機器産業連合会(医機連)産業政策委員会委員(JIRA派遣委員)
法規安全部会海外医療機器法規専門委員会/医療機器ソフトウェアワーキング委員
〇電子情報技術産業協会(JEITA)
前医用電子システム事業委員会副委員長
前医療用ソフトウェア特別委員会幹事
前医療機器産業連合会アジア分科会副主査(JEITA派遣委員)
〇保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)
前総務会副会長として一般社団法人化に尽力。
〇前日本経済団体連合会(経団連)欧州地区委員会委員
日EU EPA交渉をEU工業会(COCIR)と連携して支援。
■専門および得意な分野・研究
医療機器規制の国際ハーモナイゼイション
(IMDRF/GHWP(旧AHWP)と各国規制、EPA、人工知能・機械学習等を含むSaMD、UDIなど)
■本テーマ関連学協会での活動
〇日本画像医療システム工業会(JIRA)
前国際委員会委員長/グローバル工業会DITTA(Global Diagnostic Imaging, Healthcare IT & Radiation Therapy Trade Association)の初代ステアリングメンバーとしてIMDRFや国際薬事法規制のハーモナイゼイション活動に従事。
医療機器産業連合会(医機連)産業政策委員会委員(JIRA派遣委員)
3工業会(JIRA、JEITA、JAHIS)に属する立場から、薬機法への改正時の「医療機器プログラム」導入に向けての3J(JIRA/JEITA/JAHIS)連携に尽力。
〇電子情報技術産業協会(JEITA)
前医用電子システム事業委員会副委員長としてME機器の法規制や保険収載等の活動に従事。
前医療機器産業連合会アジア分科会副主査(JEITA派遣委員)として日本製品のグローバル化支援活動に従事。
<その他関連セミナー>
医療機器/体外診断薬の薬事・製造 一覧はこちら
日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2025年10月21日(火) 13:00-17:00 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 51,700円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき40,700円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
お申込みはこちらから
配布資料・講師への質問など
●配布資料はPDFなどのデータで配布いたします。ダウンロード方法などはメールでご案内いたします。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。
(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
※メールアドレスの記載誤りについては、以下へご連絡お願いいたします。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
→Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、カメラ・マイクが使えないなどの事象が起きる可能性がございます。お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
→音声が聞こえない場合の対処例
→一部のブラウザは音声が聞こえないなどの不具合が起きる可能性があります。
対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
(iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)
→見逃し視聴について、 こちらから問題なく視聴できるかご確認ください。(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」
<見逃し視聴ご案内の流れ・配信期間詳細>
セミナーポイント
■講座のポイント
診断支援等に使用される人工頭脳(AI)や機械学習(ML)等を利用するプログラム医療機器(SaMD)の法規制はまだ整備途上であり、承認や認証申請を目指したSaMD製品の開発は、最新の動向をつかんでの対応が重要です。
以前の講座では、「SaMD機器の申請書の書き方」の基本とともに、添付資料(STED)に沿ってポイントを具体的に解説し、基本要件第12条に関連する規格等の解説に加え、ソフトウェア部品表(SBOM)についてもわかりやすく解説しました。
今回のセミナーでは、AIやMLのトレーニングデータとなる診療情報の適切な入手に関わる方法について、最新情報を踏まえ解説を追加しました。
■受講後、習得できること
①SaMDの承認や認証に必要な申請書の書き方の理解
・SaMD機器の申請書の書き方の基本の理解
・SaMD機器の申請書(STED)の書き方の基本の理解
・画像コンピュータ診断支援プログラムの審査者への説明のポイント(対PMDA)の理解
②SaMDの承認や認証上の課題についての理解
・AI/MLを利用したSaMD機器の法規制上の押さえておくべき課題
・AI/MLを利用したSaMDの性能評価の考え方
・医療デジタルデータのAI/ML開発への適法な利活用について
③SaMDのサイバーセキュリティ規格とリスクマネジメントについて
・医療機関からのSBOMやMDS2の要求に対する対策の理解
・サイバーセキュリティ規格やユーザビリティー規格への対応とリスクマネジメントとの関連についての理解
④SaMDへの保険適用の現状と行政の動向
・医療機器の保険区分やプログラム医療機器の保険適用に向けての考え方
■受講対象
・SaMD開発技術者・保守担当者
・SaMD開発企業等の薬事担当者
・SaMDを取り扱うCROの薬事担当者
・医療機器のリスクマネジメント担当者
・対医療機関向けサイバーセキュリティを担当する営業技術担当者 など
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・薬機法(医療機器の基本要件基準第12条第3項ほか)
・JIS T14971、JIS T81001-5-1、JIS T2304
・薬生機審発1224第1号/薬生安発1224第1号 医療機器のサイバーセキュリティの確保及び徹底に係る手引書
・薬生機審発0331第16号/薬生安発0331第8号 医療機関における医療機器のサイバーセキュリティ確保のための手引書
・ソフトウェア管理に向けた SBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 Ver.1.0
・医療デジタルデータのAI開発等への利活用に係るガイドライン
■講演中のキーワード
・SaMD/AIMD/MLMD
・医療機器(SaMD)の基本要件基準
・サイバーセキュリティ/リスクマネジメント
・JIS T81001-5-1
・SBOM(Software Bill of Materials)
・画像コンピュータ診断支援プログラムの審査者への説明のポイント
・MDS2
・医療機器認証申請書の書き方
・医療デジタルデータのAI開発等への利活用
・仮名加工情報の第三者提供
セミナー内容
1.プログラム医療機器(SaMD)で知っておきたいこと
1-1.Software as Medical Device(SaMD)の適用範囲
1-2.AI/MLによる医療画像解析の概要
1-3.医療用画像へのAI/MLの利用と評価
1-4.AI/MLによる画像解析の法規制上の課題
1-5.SaMD(AI/ML)の薬事認証事例紹介
1-6.SaMD(AI/ML)の性能評価:「正解」の考え方
1-7.医療デジタルデータのAI開発等への適法な利活用について(仮名加工情報の第三者提供の法的根拠を中心に)
2.SaMD機器の認証申請書の書き方
2-1.SaMD認証申請書の書き方(基本編)
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムの一変を例として
2-2.添付文書(STED)作成に当たっての留意点
汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムの一変を例として
2-2-1.認証基準等の確認方法
2-2-2.SaMD製品の添付文書(STED)作成に当たっての留意点
・認証基準への適合性
・基本要件基準への適合性
・設計検証及び妥当性確認文書の概要
・JIS T 2304:2017/T81001-5-1:2023/T 62366-1:2022の実施状況など
2-2-3.リスクマネジメントの実施状況
3.医療機器の基本要件基準の改訂について(医療機器の基本要件基準改定12条3項を中心に)
3-1.医療機器の基本要件基準の改訂について
3-1-1.医療機器の基本要件基準 第12条第1項
3-1-2.医療機器の基本要件基準 第12条第2項
3-1-3.医療機器の基本要件基準 第12条第3項
3-1-4.第12条3項への適合性の適用に関する用語について
3-2.ソフトウェア部品表(SBOM)について
3-2-1.SBOMとは?
3-2-2.SBOMのフォーマット
3-2-3.SBOMの導入プロセス
・SBOM導入に向けた実施事項
・SBOMの作成手段
3-2-4.SBOMツールの選定
3-2-5.SBOM作成・共有フェーズ
3-2-6.SBOMに関するQ&A(通達)
4.サイバーセキュリティ規制について
4-1.サイバーセキュリティへの通達およびガイドラインの発出
4-2.サイバーセキュリティ規制 全体像と対象
4-3.サイバーセキュリティ規制 対医療機関
4-4.サイバーセキュリティ規制 対医療機器
・JIS T81001-5-1:2023の解説
5.SaMD機器への保険適用について
5-1. プログラム医療機器の保険適用に向けての考え方
<終了後、質疑応答>
お申込みはこちらから